1.青木ともじ
●
2.青島玄武
●
3.青本瑞季
●
4.青本柚紀
●
1. 夜があり 青木ともじ
あたたかや二人で運ぶ長机
飛び出さぬ飛び出す絵本うららけし
囀や跳ね奔放に書道展
入試監督きれいなこゑではじまりぬ
やはらかに廃車積まるる桜かな
桜かつ散るや上野にすこし雨
大筋は桜の頃に聞いてゐる
おとうとの家庭訪問ヒヤシンス
ヒヤシンス並べなほして退任す
春濤をひとり占めしてひとりなる
くづれさうな光を春の海といふ
生卵割る背筋まで新社員
青饅にふと深海のふかみどり
かぎろへば神奈川へゆく橋にゐる
風船を連れ不自由な体なる
夏近き空に火葬の煙残る
人類に火があり天に藤があり
白蝶を吹き消すやうに見失ふ
対岸を眺めてをれば春終る
はつ夏はさつき見てゐた雲の白
友を待つ背に噴水を感じゐる
立ち漕ぎの一歩目強き植田かな
のつぺりと羊羹倒す暑さかな
居酒屋のトイレに香水がにほふ
なきがらの金魚とろんと沈みたる
苦しんで死ねば汗なら残るだらう
ヘルメットの内側臭き夏野かな
ねむり草めざめるときの波紋めく
日傘して孤島のやうな女かな
売る籠のすべてからつぽ登山道
くちなはの来てゐて此岸広くある
何の碑か知らずありがたがつて秋
旧友は嫁いで百舌鳥の街にゐる
皿に入れポン酢あかるき良夜かな
一といふ字の潔き夜学かな
紅葉かつ散る空港の片隅に
菊の日の寺に裏口見つけけり
わけいつて山頭火忌の酒場かな
文殻のやうに蜜柑の皮を閉づ
理科室のうしろのストーブが匂ふ
実験のマスクがすこし驚きぬ
フラスコの沸騰を待ち山眠る
夜廻りのひとにちひさな橋があり
湯豆腐の波に豆腐のくづれけり
おほかたはわたしの上に降らぬ雪
まいにちの中に夜があり吹雪きけり
本に倦み二月の町をかなしうす
いつか返さうCDとマフラーと
船団がその闇にある寒さかな
火事跡は画廊の明さもて暮るる
●
2. 海神(わだつみ)の裔(すえ) 青島玄武
寝転べばあまりに天の高きこと
芒原夕陽の舟となりにけり
梨を剥く日照雨のなかを蝶が舞ふ
寂しさは楽園にあり法師蝉
名月の踊り出さんとしていゐたり
七五三も昔のことと言ふ子かな
小憎らしき頬をつねれば冷たくて
秋麗の袖に隠るる腕時計
小春日やバスいつぱいの子供たち
やおとめは初めて雪をまとひけり
木枯らしの表へ出ろと引き出され
聖菓より少し大きな聖樹かな
年の瀬のくの字に座るお人形
曳猿が晴れ着の人を追い回す
ジヤンボ機の翼の下の玉競り
鶴舞ふや久遠のの尽くるまで
熱燗を胃の腑の奥で抱き締むる
嬰の手と握手する指寒桜
春水のはしやいでをりし水車かな
経由して茶となりにけり春の水
里の子が斑雪山へと登校す
体内へ降りる階段梅真白
寒戻る寒戻るよと烏啼く
山々は膝を崩して桜草
春コート風欲しがつてゐたりけり
花影の猫となりたる夕べかな
泣き叫ぶ子供のゐたり花の宴
花満てり水面の花の散るときに
散る花へ修羅と争ふ波濤かな
お小言のまあどつさりと春の風邪
父親が怪獣となる野の遊び
連翹や海へ海へと汽車は往く
どうにでもしてよと春の大根が
海神の裔の仔馬の生まれけり
唇が歌ふ形となりて夏
旅人に旅の小路や若葉冷
掌の山河を渡る螢の火
髪筋に指先沈む薄暑かな
冷房でご飯が冷めるラーメン屋
写真屋の声の太さよ夏の富士
人殺せさうな器や夏料理
マイクにて蚊に刺されしと発表す
鼻息の急に荒ぶる泥鰌鍋
薔薇の香を嗅ぐや爪先立ちとなり
梅雨寒の切手は丹念に舐むる
プール出て生まれ変はりし女かな
トマト掴む親指までも細き手が
白南風や波が客なる自転車屋
用件を指示しながらも髪洗ふ
観音の御影を包む深緑
●
3. 山羊がゐる 青本瑞季
夏菊に閉ぢてまぶしき扉かな
南風散らかつてゐる子らのこゑ
貝殻の口を小さき蜘蛛わたる
花あやめ雨に紛るる鳥の足
梅雨晴の足波立たす団子虫
六月の書庫は階段匂ひけり
昼顔に白犀ほどの雲ありぬ
合歓の花おほきな水はよく流れ
えぞにうの腰折れてゐるところかな
白扇は後ろの森に陰りけり
煙草の箱夏痩の手をはみ出せる
その朝の海のごとくに曇る葡萄
濡れてゐる楽譜秋果の籠の下
虫籠のかたちの染みを風とほる
絵本閉づれば真葛原まで続く道
干柿に牧草昏くなりにけり
ぽつぽつと菌百葉箱の下
芒野の終はるまぎはの水飲み場
いななきに幕切れめける花野かな
おほらかに学生蔦の灯へ帰る
はつ冬の夢の合間を来る地震
絨毯に目覚めて舟と思ひけり
肉塊に糸の食ひ込む十二月
湯ざめしてみんなやさしい電話口
風邪気味よ歩みに鳩のちよつと飛び
初雪やサドルひと拭きにて乾く
冬ざれの盲点として秩父の牛
火事場帰りの胸元にペン差しなほす
倒木を容れぬ浅さに水温む
春の白鳥ひらがなの受肉とも
ぐつぐつと混みあへる夜の残る鴨
春の日に睡られずゐて湖を過ぐ
踏青の見知らぬ墓地に来てしまふ
蘖が幽霊よりもどつとある
汐干狩続けることの憎むに似
つぶ貝を焼けば電話を待つやうな
しんじつは日より冷たし干鰈
茶筒固くて永き日の座敷かな
からだぢゆうのみづがねむれりうららかに
花なづな鳥の足あと乾きつつ
羊蹄や汀てふもの川にもあり
たんぽぽの絮散る笛のもつれる音
パンジーの花ふてぶてし地を擦つて
白蝶よかぼそい泥の脚を上げ
とどまりて髪ぬるくなる虻の岸
春休四方がさぼてんにて座る
しだれざくら舟に届かず雨のなか
菜の花の中の蛇口の涸れてをり
黄水仙天国なら散らかつてゐる
春落葉懐かしさうに山羊がゐる
●
4. 消えろ 青本柚紀
砲錆びて芽吹きはじめの山を向く
この昼の囀の木であることよ
人がゐてミモザはいつまでも渚
川は流れて柳に触れし無数の手
電気ブラン飲みたし蝶に溺れたし
空腹に慣れて桜が白いのだ
たんぽぽの絮を奪へばひかりにきえる
春休読書のあとに釘打てば
食堂に溜まり春愁なき君ら
山のうしろははや花過ぎのけふである
花散らす力を沖に太宰の忌
見つめあふやうに新樹の明けてゆく
まつくらな門をくぐれば薔薇に着く
いちまいの葉をいくたびも迷ふ蟻
句は縦書き初夏の修道女のやうに
十薬の茂みを日々はひきかへす
泉見て四肢の時間のゆたかなる
女子寮に殖ゆる噂よ夏落葉
火蛾と火蛾ぶつかる夜を醒めてゐし
夏痩に渋谷の音の押し寄せる
箱の虫うごき夜学は力学へ
秋雨の受話器の奥の息づかひ
待てど来ず秋刀魚の骨を外したる
名月を山手線の廻りをり
通信の絶えて桔梗をまじまじ見る
大学へ傘が秋思が重なりあふ
束ねたる手紙信濃は霧の中
弦楽に林ひらけて秋逝けり
冬の噴水割れて一羽の鳥が発つ
いくたびも指が時計に触れ枯野
尽く冬の灯にして小さき部屋
そのことを問へば白息がちとなる
祝はれてゐて室咲のあをざめる
はばたきは微かに枯葦の日ざし
毛糸編む絵の少年と語りつつ
ふくよかな道にて竹馬のすすむ
枯枝を踏み折る空の深さかな
缶詰の尽きれば霜の声さやか
見せたしと思へば鴨がどんどん発つ
枯木まで来たり枯木を引きかへす
冬の木を書いた言葉で死ねるだらう
閉ぢてゆく森早春の声がある
蘖の幹いつまでも水浸くなり
永き日の座せばさざめく遠くかな
墓がある恋猫のゐたこの庭に
風船の力をゆふぐれに還す
月下細魚はだんだん白い鳥になる
今日までの山河を忘れたい辛夷
言ひ得ないことが菜の花より多い
新宿はすべて雑音 消えろ蝶
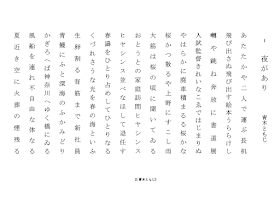











0 件のコメント:
コメントを投稿