5.安里琉太
●
6.生駒大祐
●
7.大塚 凱
●
8.仮屋賢一
●
5. 昔見たやうな 安里琉太
雨粒の山蟻を押しながしけり
風鈴やたくさんの手と喉仏
人待ちに薔薇の匂ひのする頃か
ぱりぱりとプールサイドの身を起こす
青林檎ひとつの雲の引きかへす
浜のもの錆び付いてゐる昼寝かな
その石のむかしからあり南風
サングラス一人になれば胸にさす
髪灼くる巨船を鳥の旋回し
文弱の父に冷酒の夜の永し
糸瓜棚暑くなる日の雲の形
竜頭巻く掃苔の水汲むあひだ
蓑虫や雨うつとりと痩せてをり
鵙啼きて旋毛の並ぶ理髪店
言はれなきこと秋草にわが父に
敗荷になまくらな水かがよへり
蝶に似て此処も風吹く茸かな
中空の雨の真白き猿酒
茸山どの木も昔見たやうな
川底に一縷の草や神無月
セーターや胸の英字に所以なく
温室の道へ這ひだす赤き花
書きだしのすでに日暮れて浮寝鳥
二日はや肉の記憶が舌のうへ
火の糧にならぬ花弁や山始
日溜まりの水となりけり雪兎
悴みて水源はときじくの碧
忘れじと書く寒林の途中から
春暁や何の忌となく雨が降り
闘鶏師大き時計を掛けにけり
よく晴れて蕨の下は苔の国
永き日の椅子ありあまる中にをり
清明や魚のぬめりのうすみどり
払へどもみづの吸ひつくさくらかな
紙風船喪の一団が暗がりに
桜湯に彼方の波の白むかな
花過のみづの匂ひに憑かれゐし
空腹が蝶を無残に見せてをり
潮干狩雲の写真のどれも似る
ポケットの闇揺れてゐるがうなかな
春暑し蜜吸ふ茎のうすら紅
江ノ島の日傘の白く混みあへる
夏芝に寝て笑はれてをりにけり
噴水にもつとも近きベンチかな
手庇のなければ見えず五月の塔
昼寝覚とほくの音のぽつぽつと
老鶯や斜めに弱る竹箒
亡きひとの写真のきよら団扇風
登りきて涼しき景となつてゐし
薔薇濡れてこゑのるつぼの真ん中に
●
6. 冷たき花 生駒大祐
鳥ゆける空のてまへは雪の街
やうやうとして初夢の橋渡る
牛肉に曇りぬ寒の銀食器
丘の冬木すでに憂ひのかたちなす
山冴えて里呆けたる野蒜かな
たれもみな裸足に生まれ野は紫雲英
とくとくと色流れ出る雛の家
子供来て死を言ひそめし椿かな
凡庸な西の風吹く蓬かな
眠るべく便箋ひらく鳥の恋
揚羽踏む真昼を映す潦
鯉抜けし手ざはり残る落花かな
花過を眠ればうをにまた近づく
蝶舞ふや撥条をもて時動く
筆立に筆を待たせて春ゆきぬ
金澤の五月は水を幾重かな
雲去れば力抜く空山法師
上京の夜は新樹さへ冷えゐたり
列車の灯糸引きて去る緑雨かな
筍を煮てゐる白き時計かな
明るさに箒たふれし白牡丹
はつなつを夜の友訪ふはなんとなく
水輪広がる梅の実をたなごころ
瓜の花冷たし水の中の手も
呼び止めし汝は何用夏蓬
蝸牛来ては波立つ月日かな
蜘蛛の糸ときをり水に触りけり
風にして午後しづけさの立葵
雨ながら外用の夏薊かな
花菖蒲自在に白をあつかへり
触れて消す灯も夏雨の夜なりけり
空蟬のこぼれて今朝は波のうへ
はしやぎあひつつ夕立の縁へ逃ぐ
刻々と雨になる屋根花木槿
夏風邪にあらはれて直ぐ薬缶へ火
草に遣る湯呑の水も晩夏かな
玻璃さつとあをざめる秋立ちにけり
雁ゆくをいらだつ水も今昔
餉の梨といま水中の刃物かな
かげろふや天才にして長き生
霧雨や汝を疎みては幾鏡
十月も末のかの絵は買はぬまま
椎の実を拾ひしままに渚まで
湖は拙き波の草紅葉
紅葉鮒身じろぐ水の粘りかな
飽くるなき大空や枯芝に寝て
大根の餉に思はずの言葉かな
目瞑るにわづか足らざる霜の花
大笑のつひの涙を炬燵かな
寒鯉の目覚めて意味を離れけり
●
7. 白 大塚 凱
逢ふたびに微かに老いて朴の花
白シャツを脱いでも燈台が遠い
素裸になつて欅にすこし似る
飛込の音が吸はれて樹のみどり
献血ができないからだゆゑ泳ぐ
浮輪から獣のやうな息を抜く
恋びとを砂丘とおもふ午睡かな
仙人掌に夕星ほどの花きざす
帆と見えて鳥は涼しい距離にゐる
虹の脚わたしのゐない街に立つ
乳母車蚯蚓をいくつ轢いてきた
腕時計灼けて帰つて来ない鳥
迷ひ子のときに花火をふりかへる
八月の鋭利な雨に船を待つ
帰りくる帆があり秋の名もない帆
もの言はず墓参の父にライター貸す
踏切はカンナを揺らすために鳴る
かぎりない椋鳥の見てゐるつむじ
秋よ詩を読むこゑが思つたより若い
週刊誌の女に露が沁みてゐる
学問は月に背くといふことか
蚯蚓鳴くランプが冷めてゆく時間
明けながら野のひろがつてゆく檸檬
恋そして吹かれてやまぬ真葛原
胸がちに東へゆけば霜鳴れり
枯野から白い畳にゆきあたる
龍の玉さぐりて泉汲むこころ
抱き締めても石焼藷のやまぬ湯気
買はれゆく聖菓の白を鳥と思ふ
野良猫に眠るべき箱クリスマス
嚔してこころ曇天へと紛る
さびしさが森からやつてくる毛布
古日記大海深く夜を蔵す
うつくしい文がおほきな火事になる
そのみづのどこへもゆかぬ火事の跡
冬の壁さつき見た木を忘れてゐた
傘の骨からつはぶきの花になる
爛爛と雪眼をひらく夜行バス
丘へ来て雪解のペンが走り出す
二月ひとり碇のやうな辞書を買ふ
窓枠に蜂死んでゐる大試験
如雨露から虹があふれて赤黄男の忌
絵に描いてゐるとさくらが壊れだす
暮れかねてゐる抽斗のやうな母
鳥の巣をくづず月光かもしれぬ
柳その奥へ遊びにゆくおとな
春服をならべて夜がありあまる
花の名の女よ朝寝してゐても
捨てられた椅子を見てゐる新社員
肺ふたつ労働祭の風の中
●
8. ふるきづ 仮屋賢一
竹馬を道間違へて降りにけり
だんだんと赤の他人へ雪だるま
社長まだ法被着馴れず寒造
神の座の光を纏ひ追儺の矢
郵便配達ふもとの霞率ゐて来
海苔船の海苔を払ひて舫ひけり
声色といふ色ありて石鹸玉
卒業の列つぎつぎに傘たかく
まづは眼の春塵拭きて閻魔像
春の風邪冷ましすぎたる湯を沸かす
啓蟄のゲームカセット吹いて挿す
呼べばすぐ開く写真屋つばくらめ
はんぶんは辛夷のはうへ海の風
煉瓦棟赤く旧りゆく雪柳
鶯の飛ぶまへ力抜いて鳴く
真ん中に要らない器械ある飼屋
木匠の飼屋の梁の覚書
どこからか濁流となる鳥曇
護符多く吊せる鞄青き踏む
遠足や草で拭きたる靴の裏
叩くたび皺の増えゆく紙風船
売り切れてしばし風船売のこる
宙のものすべて軽さう花菜畑
後ろよし前よし花菜よし発車
草笛のだんだん下手になつてゆく
鯉のぼりおろしてさつと撫でてやる
全身を扇で指して確認す
きづすぐにふるきづとなる実梅かな
宮の樅山を突き出で大夕立
かき氷親子の匙の入れ替はる
神還すのちの神輿の重きこと
月下美人老いたるまへに仕舞ひけり
ゆるやかに坂のはじまる桔梗かな
竹の春行幸の碑に折りかへす
鶏頭を過ぎて話し手替はりをり
記念写真案山子いちばんいい笑顔
美術展部屋の真ん中ぽつかりと
近きほど自棄に描ける曼珠沙華
源流にものの沈まず松手入
長音に曲を終はらせ冬支度
ネクタイに鋒ふたつ冬に入る
埋火や仏描くに音の無く
裏方は靴を履きたる聖夜劇
絨毯をはみでて寝言おほき犬
柴漬を見まはる嵐山の風
懸想文売札束に札仕舞ふ
懸想文もらひて犬によく嗅がる
すずしろのつひでに菘切られをり
初弘法店主と雨を案じあふ
連載の明日にはじまる福寿草
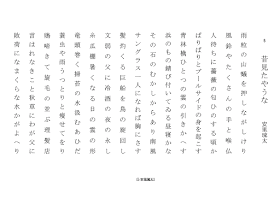











0 件のコメント:
コメントを投稿