それは通俗性の問題ではないか?
上田信治
「俳句」2019年6月号を読んで、俳句と通俗性ということを考えた。
それは、神野紗希による連載時評の6回目と、「大特集「U(アンダー)39作家競詠 推薦!令和の新鋭」」を、読んだことによる。
●
神野紗希の時評「現代俳句時評⑥ ミューズすらいない世界で──俳句とジェンダー(上)」(「俳句」2019年6月号 p.179)は、フェミニズムの観点から、まず、歌壇における男性偏重的な短歌観・短歌史観が、その下の世代からきびしく批判されていることを示し(参考:こちらとかこちらとか)、その上で、俳句にも同様のことはある(しかし問題として意識化されていない)というふうに、進んでいく。
子にもらふならば芋煮てくるる嫁 小川軽舟
「鷹」二〇一六年十一月号掲載の一句。息子が妻をもらうなら、芋を煮てくれるような素朴で優しいお嫁さんがいいなあ。無邪気な願望をほほえましいと受け止める人も多いだろう。しかし私はこういう句を見ると、真綿で首を絞められたような窮屈さを感じる。今も社会に横たわる、家庭的な女性への欲望、保守的な思想を感じる。そうか、やっぱり芋煮てほしいのか。「そもそも嫁を「もらふ」発想自体が、かつての封建時代の家同士の結婚を思わせる。むしろ時代後れだからこそ「昔はよかったよね」とほほ笑み合いたいのかもしれない。(神野紗希・前掲文)
自分は、ここで神野が感じたことを、全面的に首肯する。しかし、ジェンダーの問題とは、また別のことを思う。
それは、こんなにも、俳句に通俗性がフリーパスで存在していいのだろうか、ということだ。
●
神野に句を引用された小川軽舟は、かなり意識的に「通俗性」を取り入れてきた作家だ。
そのことは、自選十句に
平凡な言葉かがやくはこべかな 『手帖』
死ぬときは箸置くやうに草の花 『呼鈴』
が入り、
水たまり踏んでくちなし匂ふ夜へ 『近所』
燃えほそる燐寸の首や夕蛙 『手帖』
が入らなかったことからも、うかがえる。十句に〈泥に降る雪美しや泥になる〉は入っているものの、この傾向の句はこれ一句だけなのだ(『俳句』付録「現代俳人名鑑」2017)。
それは、「鷹」主宰継承をきっかけにした転換だったのかもしれない。
湘子が亡くなって私は自選に頼るしかなくなった。しかし、主宰の作品が守りに入ってはいけないと臍を固めた。これまでの自分の作品と違うところも攻めようと考えた。(「シリーズ自句自解ベスト100 小川軽舟」p.157)
という小川自身の述解もある。
これは〈蝸牛やごはん残さず人殺めず〉の自解なので、その作風の転換は「しほり」と呼ぶべき繊細さから、軽いアンチヒューマニズムを経て、正面切ってのヒューマニズムへ進んだと想像される(もちろん、第一句集にも〈自転車に昔の住所柿若葉〉のような句はあるが)。
そうして小川軽舟は(湘子が一日十句の時代に目指したように)、自分の作品を「太く」していったのだろう。
自分は読者として、軽舟の「しほり」の句や〈ごはん残さず人殺めず〉を深く愛するので、たまに凄みを見せてくれてもいいんじゃないか、と希望したりもするけれど、多くの会員が共有すべき価値の中心として、その転換は必要なことであったに違いない。
晩春やわが鞄置く妻の膝 小川軽舟 (「鷹」2019年6月号)
近作。微笑ましい景といえるだろうけれど、この句の価値の存するところは、やはり通俗の範囲に違いない。
●
件の時評を読んだある若者が「神野さんが問題にすべきは、高柳さんではないのか」と言ったと聞いて、自分はほぼ爆笑した。
そして、髙柳克弘も、自分にとって(ジェンダー意識もさることながら)その通俗性が、ひじょうに気になる書き手だ。
もう去らぬ女となりて葱刻む 髙柳克弘『寒林』
これを読んで紗希さんが「なめんな」と思わなかったわけはないと思うのだけれど、それはよけいな御世話だとして、この物言いが旧弊であることは、おそらく作家の設計図のうちに含まれている。
ぬけぬけとそれを言って「色悪」としての自画像を描いてみせました、という句なので、その通俗性をまとう身ぶりが、わざとであることは間違いない。
しかし、わざとだから、この句が通俗的ではないとは言えない。「ぶってる」ところも含めて、句の価値の射程が大衆性の範囲に収まっていることにかわりないからだ。
岸本尚毅が、髙柳を「波郷や湘子のプロ根性を受け継ぐ」と評したのは、このあたりだろう。
そういえば、髙柳にも〈あぢさゐや日はいちにちを水の上〉〈綿虫に平日の人どほりかな〉のような繊細かつ高踏的な句や〈ビルディングごとに組織や日の盛〉のようなナンセンスがあるので、『鷹』の二人の振れ幅は、驚くほど相似している。
●
さっき、思わず「大衆」とタイピングしてしまったけれど、「通俗」を問題にすることは、エリーティイズムの立場に身を置くことなので、しかたがない。
「通俗」を定義するなら「表現物の価値(よさ)が、水準を低めに見積もった読者(=大衆)の、了解の範囲内にあること」とでもなると思う。
ある日のツイッターから引用するけれど、
https://twitter.com/fd_m_n/status/1130718932929671168
というのは、本当にそのとおりで、自分が高く評価する〈ヒヤシンスしあわせがどうしても要る 福田若之〉にも、通俗に近い分かりやすさがあり、ポピュラリティは高いけれど、それにとどまらないものがあるというだけだ。
では、自分は、なぜ、俳句の「通俗性」を、問題であると感じて、引っかかっているのか。
●
「大特集「U(アンダー)39作家競詠 推薦!令和の新鋭」」(同号p.49)は、ここらで、結社内でがんばっている若手にスポットを当てましょうという企画。
39歳以下の書き手が24人、結社主宰の推薦を受けて(「群青」と「晨」は準結社の扱いらしい)、新作20句と旧作25句(主宰選)を掲載している。まさに大特集というに、ふさわしい。
通読した。新人(とされている)書き手の作品をあげつらうのも申し訳ないので、個々の作品には触れない。
しかし、その作品は全体に「通俗性」が濃く、ありていに言ってしまえば、それは結社の問題なのではないか、と思ったのだ。
以前、自分は「ku+ 2号」において、俳人地図の作成を試みた。
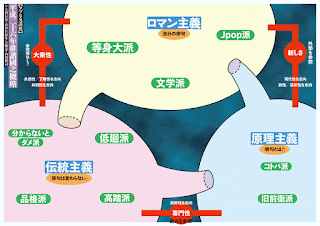
「平成二十六年俳諧國之概略」(「ku+2号」2015年8月)※人名の入った画像がみつからず白地図。
参考「ku+2号」付録 「(略称)俳句界map」 を、読みほどく
同時代作家を「伝統主義」「ロマン主義」「原理主義」の三派に分類したわけだけれど、じつはこの図、対角線で区切って、左上サイドが「大衆性」のエリアであり、対する右下サイド全体が、新しさと専門性からなる「高踏性」のエリアになっている。
今回登場の24人の書き手を、同図上に配置するなら、大半が左上サイドに貼りつくように、「ロマン主義」内の「等身大派」から「伝統主義」内の「分からないとダメ派」のエリアに、マッピングされるだろう(※何人かは「ロマン主義」の真ん中から右寄りにくる)。
代表的な作家として(またしても)名前をあげさせてもらえば、石田郷子、津川絵理子、小川軽舟、片山由美子、櫂未知子、彼らが位置するエリアに、この若手達はほぼ入ってしまう(おそらく、彼らの大半は、これらの代表作家に並べて語られることを、当然であり、栄誉であると感じるだろう)。
今回の新作が通俗的ではないとはっきり言えるのは、田中裕明的な高踏性を志向する柳元佑太くらいだろうか。
逆に多くの書き手が、作品の価値を損なうほどの通俗性を帯びているように思えた(全員ではない)。
●
『俳句』6月号からは離れるけれど、岸本尚毅が、第10回田中裕明賞の「選考委員の言葉」として(候補作のいくつかの句をあげ)、
(…)「気の利いた言い回し」が使われているが、しょせん底の浅い面白さでしかない。この種の「書き急ぎ」は読者の読みの深まりを妨げるものでしかない。この種の言い回しが俳壇に流行るとすれば、それは作者でなく、褒める人の責任である。次回以降の選考委員の皆様には、俳壇に流布されがちな「一見上手そうな句」を安易に褒めないことを、強くお願いする。
と書いた。岸本は、作品評の言葉を極めて慎重に選ぶ人だと分かっていたので、この直截な厳しさには驚いた。
http://furansudo.com/award/2019/2019.html
それに応えて、ある若い書き手が、ツイッターで
「岸本先生のメッセージ。ほぼ、名指。しかし、引き継ぐ選考委員のみならず広く若手に向けられているメッセージ」
と書いた。
名指しというのは、次回から裕明賞の選考委員となる4人のうちのいずれかということだと思われる(自分には、髙柳さんのことではないように思われる)。
これも、通俗性の問題だろう。
●
俳諧連歌よりこのかた、私たちの五七五定型詩は、雅俗の葛藤において生まれ、また生まれ直して、発展してきた。だから、通俗であること、大衆的であることが、俳句にとって、必ずマイナスであるわけはない。
ただし、とりわけ現代において、七五調は俗謡のリズムでもあるので、内容が一線を越えて俗にかたむくとき、そして、形式との関係が緊張を失うとき(「雅俗」の「雅」が見失われるとき)、その句には、チョイナチョイナとか、ハーどーした、どーした、と掛け声がかかりそうになる。
十七音は、ハハのんきだね〜といった、鼻唄的いい調子に堕する危険を内包しているのだ。
その掛け声を斥ける強度というものが、たとえば〈湯豆腐やいのちのはてのうすあかり〉(久保田万太郎)には、ある。〈ヒヤシンスしあわせがどうしても要る〉にもあるだろう。〈平凡な言葉かがやくはこべかな〉は、どうだろう。〈一瞬にしてみな遺品雲の峰〉(櫂未知子)は、〈双子なら同じ死に顔桃の花〉(照井翠)は、どうか。
それは、つまるところ、読み手次第ではあるとはいえ。
この十年、俳句においては了解性と共感を重視する傾向が強く、その帰結としての、通俗性の肥大が、見られるように思う。
通俗=ポピュラリティは、もちろん、必ずしも悪ではない。
しかし、小川軽舟が結社を率いる過程で、そのポピュラリティを肥大させていったのだとすれば、そして、結社推薦の若手の多くが、通俗に堕することへの怖れを持ち合わせていないように見えるとすれば。
俳句における通俗性の問題は(他のすべてのイシューと同じく)、いかなるコミュニティを宛先として書くか、という問題に帰するのだろう。
●
結社で書いている新しい人に言いたいのだけれど、そのコミュニティの多数派がよろこぶものを書くことからすこし離れて、あなたと同じように新しい人たちを宛先として、考えてもいいんじゃないだろうか。
一度くらいは。
●

0 件のコメント:
コメントを投稿