2016「角川俳句賞」落選展■第4室
13.すずきみのる
●
14.高梨 章
●
15.滝川直広
●
16.ハードエッジ
●
17.古川朋子
●
13. 追記 すずきみのる
砲丸の手を離れ飛ぶ麦の秋
初夏の笑顔並べて医学生
老鶯や竹乱れ生え屋敷林
車道へと歩みやまずよ黒毛虫
声といふかたまり吐きて牛蛙
海が呑む浜昼顔も砂浜も
沸騰の一山にして新緑す
雲海の開けてダムとその湖と
緑陰や押してツインズ乳母車
白シヤツに翳りとなりて透く身体
いきもののいきれぬけたる繭しろし
われを呼ぶその朝声も秋めきぬ
雲母摺床にならべて処暑の餐
大路小路みごとに暮れて鉾祭
深吉野のつくばねの実を見しが縁
わたくしへと戻る途中や草の市
大玻璃に鉄線透けてゐる月見
一山を蒸し籠めの霧湧き立ちぬ
ロボットは性別不詳をとこへし
山の夜の酩酊深し猴酒
落ち鮎を食せ再々婚の友
浅漬の大根甘しワイン美味し
民家途切れし通学路峡氷雨
枝打のひとりは声の響くのみ
三山とならび称されつつ眠り
ほうと闇ほうほうと闇木菟いづこ
金色世界銀杏落葉と老幹と
スタンプを押して旅信や冬の虹
裸婦像の丸き肢体や冬の苑
寝具敷き終え湯たんぽの盛りあがり
月代やポケツトのもの当ててみよ
顔見世の鳥屋のあたりを伺ひぬ
山の影海に浮かべて初日の出
目を閉ぢて夢見の景を初景色
飾取り常の玄関へと戻る
行きずりの一人として若火見る
胴長の猫の斑の背に牡丹雪
はるあけぼの牛乳の膜しわみゐて
口移しにて春祝ぎの言の葉を
春のゆめ異郷にロバを商ひて
春灯そば湯に雲のごときもの
ケチヤツプの赤春昼の食見本
面構へ白眼なせる恋の猫
めまとひの堆肥の湯気の中に渦
揚げひばり吐声に色のあるごとし
げんげ田に音ばらまきてヘリコプター
春光の灯台のみが記憶の島
死に近き人を囲みて春障子
くつあとのかすかに続く花筵
朧夜や水面に浮かびくる記憶
●
14. 宇宙の犬 高梨 章
永き日や壺まだ口をあけてゐる
アカシアの花ふんでゆく牛飼座
てふてふは空気のなかをはかなげに
たかくたかくヒバリは空に立つたまま
ヒバリ鳴くこはれてしまひさうに鳴く
揚雲雀おりてゆけない夢を見る
日向から出てゆく春の落葉かな
うぐひすのこゑや足なが蜂がゆく
春の日や灰皿の灰やはらかし
沈丁の花風に置かれゐたるかな
石ふたつ空席となる春の丘
ふるさとはひばりのこゑのしたにあり
ひとのすがたでヒバリながむるこの世かな
くるぶしをさはられてゐるれんげさう
白木蓮しまらく風にさはらせず
さはつたところにさはられたあと春の雪
ことごとく椿のかたちで落ちてゐる
春の闇犬に鳴かれて立つてゐる
幸福は枯葉のにほひ春の朝
春風や洗濯バサミなくなりぬ
てふてふを手ばなすやうに春はゆき
うへを見てうしろへさがる金魚かな
石置けば石にちかづく金魚かな
ゆふやけとなるまへ水を散らかして
糸とんぼ見てゐし草のすき間かな
大蟻の視野へわが足入りにけり
泣いたあとのやうな気がする金魚かな
金魚ゐぬところへ行きたい金魚かな
靴下の足音もある夏座敷
鳴きやみし木にまづおりてくる夜の秋
朝顔にあさがほのつる触れにゆく
草の花ちがふ高さの高さかな
見まはしてほかにはたれも草の花
水面はとても薄くて木の実落つ
木の葉ふりつねに明るい出口かな
つかまつて鳴いてゐたりし秋の蟬
あらはれて蜻蛉出てゆく空家かな
天高し空をうごかす雲ひとつ
木の実ふる下に地蔵ありてこつん
出られたらとおもふ胡桃の外に出る
表面にふとあらはるる秋の風
泣くこともできる秋の夜の食卓
秋の夜の帽子のなかの無言かな
露の世はしづかに下着ばかり干す
カマキリにあるかもしれぬかすれ声
望の夜のくらがりに立つ空気入れ
水を乱し水鳥うかむ北半球
水鳥もみづのせなかに寝しづまる
水鳥は水にかくれてしまひけり
湯ざめして宇宙の犬のことおもふ
●
15. 栞 滝川直広
草の岸きのふの雛とどまれり
春陰を漉き込まれたる出雲和紙
フェルト地の帽子に春の雨の粒
鳥の脚洗ふ流れや復活祭
さへづりや糊の利きたる衿立てて
まだ鳥の入らぬ巣箱雨したたる
ぬかるみを作務衣飛び越す鳥の恋
海のなき街のデパート蒸鰈
乗務後の車掌たたずむ山桜
夕桜土洗はれし一輪車
雲水の下駄ひくく鳴る養花天
やすらひの花傘の柄を地に着けず
北窓の下に稿書く遅日かな
砂時計遅日より時取り出だす
手鏡のうすきくもりや遠蛙
はこべらの際まできたるにはたづみ
武者人形手綱をさばく指細し
青梅に殻のやうなる薄き翳
五月雨や紅さわがしき中華街
ぬかるみを踏んで見にゆく半夏生
転舵するヨットの海をつねるごと
鳥除けのCD吊つてあるヨット
波がしらなき波つづく油照
さつきまで蛇ゐし岩に腰下ろす
夕暮が水に溶けだす金魚玉
灯のくらき歌舞練場の花氷
月光を浴び餅肌のなめくぢり
落蝉の翅を栞にできぬかと
錆釘の土よりのぞく糸瓜棚
秋草の穂より光の去りやすし
秋高し蛇口にお礼言ふこども
秋の日を編み込んであるおさげ髪
風向きの変はりて萩の揺れ直す
野も海もある能舞台鳥渡る
棘折れて洗濯槽の草虱
額縁の鍍銀をみがく鵙日和
冷ややかな灯を積み上げてホテルなり
杉玉の鳴らぬさびしさ水澄めり
火に落つる獣の脂冬来る
御火焚やそだちきつたる火の澄みて
焼藷屋にほひの罪の軽からず
冬の蝶あさき眠りをきれぎれに
天頂を雲のしりぞく初御空
休みつつ淑気を進む松葉杖
日は透り月影こもる氷柱かな
待春の日差しまみれのさかあがり
おのが身に風ひきうけて麦を踏む
一輪の水仙の香に糺さるる
遅れゐる一羽を待てり春の鴨
雛の間の朝につかふ棕櫚箒
●
16. 半丁 ハードエッジ
地虫出て安土桃山時代かな
幼くてお玉と呼ばれ蛙の子
蝶生れて日当る石を懐しむ
さざ波を飛んでつばくらつばくらめ
春の草早も兎の耳の丈
今日こそは晴れて桜の出番なれ
咲き満ちて花の洛中洛外図
湯あがりのほろりと花よ花びらよ
花びらが吸取紙の上にかな
ならばこの紫雲英畑を買はぬかと
石鹸の刻印深き立夏かな
鯉の背に跨る五月来りけり
満ち足りて水田明りの水田なり
頭を上げて裳裾を引いて蝸牛
毛虫とは似ても似つかぬものとなる
蓮の花蜂かと見れば蠅がをる
灯台を廻る楽しさ夏燕
涼風とよくすれ違ふ日なりけり
ねたましや夕立の中を駆け行くは
うたかたのうすきみどりのソーダ水
囚はれの身をからからとラムネ玉
赤に黄に高さを競ふかき氷
割箸が置かれ冷奴が置かれ
丁半の博打半丁の冷奴
蛸足や肉の真白を胡瓜揉み
風に乗ることの哀しき祭笛
朝顔や歩いて通ふ勤め先
石ころを掃きたる秋の帚かな
髪乾くまで月の出を待たせある
満月や永遠に零るる崖の土
蓋開けて月の光のオルゴール
明月はけふ明日はあしたなり
青い目の人形青い目の野分
豊年や翅持つものは飛び廻り
色鳥を吹き消す風となりにけり
聞く耳を持たぬ人にも蚯蚓鳴く
プリズムの傷だらけなる夜食かな
子規庵の寝静まりたる糸瓜かな
神の旅大きな月を掲げたる
赤々と火中ありけり夜の焚火
膝の辺に猫より丸く毛糸玉
白鳥の湖に行き浮寝せむ
大根を抜きつ大根抜かれつつ
枯草の中の針金曲り錆び
降雪や花壇を囲む赤煉瓦
自転車の硬きタイヤも年用意
読み返すことの楽しき古日記
花のごと雪ふる中を宝船
屈強の白を重ねて鏡餅
どんど火の崩れむばかり崩れたり
●
17. 逃水 古川朋子
新緑や椅子に聖書を入るる場所
丸窓を緑の雨の充たしゆく
言問のさなかにはかにほととぎす
あしうらに砂の微熱や麦の秋
点になり線になり五月のとんび
廃墟つきぬけて新樹のそよぎけり
丹田の青むまで吸ふ若葉風
うつむいてゐればいつしか夏の海
ひまはりを見てゐるだけの停車かな
木の卓のらくがき青し百日紅
黄のアロハシャツ跳んで取るフリスビー
触るる手に傷ひとつある花火かな
白靴の赤い靴底とほざかる
朝顔や海に向かひて社員寮
秋暑し神社の鳩のふとりたる
西瓜食ひ終へし話のつづきなし
本棚に活字押しあふ残暑かな
匙に乾く一滴の水秋きざす
裸婦像の乳房を削り初嵐
いまだ見ぬ街の多さよ秋の蝶
少年のなごりの眉を秋の風
千々にものおもへば遠き花野かな
そぞろ寒となりに鶴を折る家族
夜通しの雨音に秋惜しみけり
かはほりの骨にあまねく冬来る
水の輪を毀して鳰が鳰に寄る
きれぎれに鳴るクラクション冬の虹
酢海鼠や逢へばかなしくなるをとこ
落葉掃く道をへだてて会釈して
枯枝の震へや鳥の睦みあふ
畳まれて雪の窓辺に車椅子
怒つてゐる嚔笑つてゐるくしやみ
暖簾のゆ二つに割つてクリスマス
剥製の熊に白息かけにけり
ねむるまで寝息をきいて小晦日
亀が首のばしてもどす去年今年
旅初うごく歩道の弾みけり
海に出でて国道細る水仙花
春雨や肘ついて割るピスタチオ
香水もなく花もなく猫の恋
水草生ふコンクリートの川底に
春分や日の丸なびく家しづか
春の夜のふせて置かるるマグカップ
外階段ひなぎくに行き止まりたり
桜蘂ふるドアノブにビニル傘
泪では落ちぬマスカラ雲雀鳴く
さみしいと先に言はれし春の月
背凭れに人のぬくもり鳥雲に
道迷ふたび逃水を追うてをり
手かざせば水流れけり春の雷




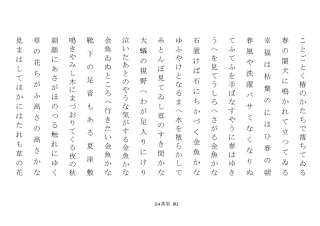










0 comments:
コメントを投稿