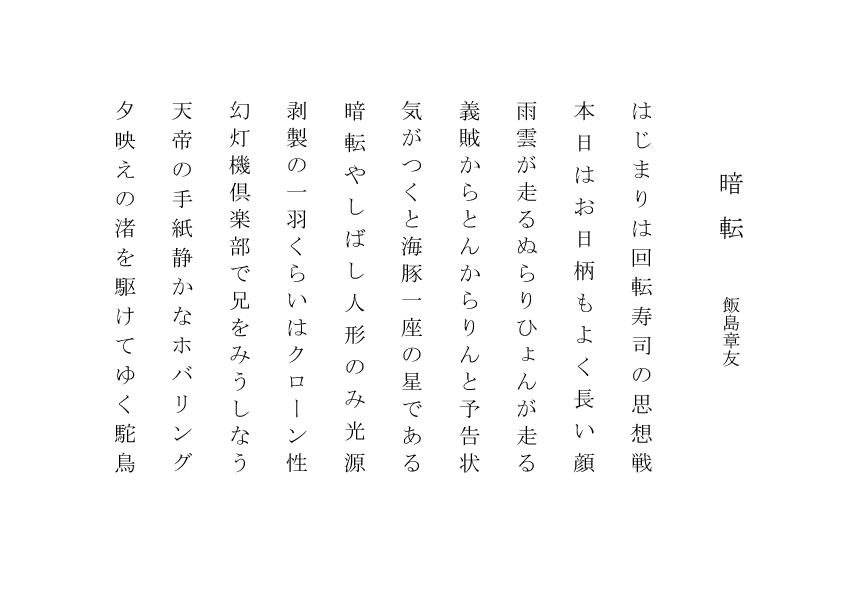2022-06-26
〔今週号の表紙〕第792号 花菖蒲 飯島章友
Posted by wh at 0:02 0 comments
2018-06-17
【柳誌を読む】チンドン屋のゆくえ 飯島章友『恐句』の一句 西原天気
【柳誌を読む】
チンドン屋のゆくえ
飯島章友『恐句』の一句
西原天気
東口と聞いて、どの駅を思い浮かべるかは、人それぞれの経験によるのだろう。私の場合、新宿。昔も今も新宿での行動は、東口が起点となる。習い性のようなもので、京王線を多く利用する今も変わらない(京王新宿駅を降りて連絡口を抜けJR新宿駅東口を出る)。
さて。
チンドン屋東口から洞窟へ 飯島章友
チンドン屋の/同時に句の、行き先として、洞窟は、東口の都会性との落差もあって、鮮やかな意表。
漂泊者の妖しさと洞窟の冥さは、イメージ的によく連関する一方、「洞窟だと人はいないだろうに。宣伝機能は果たせないだろうに」といった弛緩も働く。結果、多声的(ポリフォニック)な一句として響く。
掲句が収められた飯島章友『恐句』(2016年5月22日)は、B5判1枚を2つ折りにした中面に16句が並ぶ個人誌。解題的に「既発表作品の中から恐ろしげな川柳を選び出し(…)」とある。チンドン屋の句は、例えば同収録の《コンビニの冷蔵棚の奥の巨眼》といった直球的に恐ろしげな句とはすこし趣が違う。
ところで、俳句分野でチンドン屋といえば、八田木枯。第一句集『汗馬楽鈔』(1988年)に《鳥交る世にチンドン屋ある限り》の一句、最後の句集『鏡騒』(2010年)に《チンドン屋末法の世の鉦を打ち》など4句が残っている(生涯のテーマのひとつだったのかもね)。
八田木枯が、飯島のこのチンドン句を見たら、どう言うだろう?
ご自身のアプローチとはずいぶんちがうが、きっとおもしろがったと思うな。
Posted by wh at 0:04 0 comments
2017-01-29
ことばの原型を思い出す午後 飯島章友の川柳における〈生命の風景〉について 小津夜景
ことばの原型を思い出す午後
飯島章友の川柳における〈生命の風景〉について
小津夜景
1. はじめに
飯島章友の川柳を読んでいると〈捩=ぐにゃぐにゃ〉ないし〈熟=ぐちゅぐちゅ〉した質感をしばしば目にします。
線という線のメビウスたる地平
ほっておけ徘徊中の月だから
惑星が搗ち合いやまぬ渋谷、雨
地上では蠢くものが展く地図
ねじれたラインの入りくむ「地平」。ぐるぐると動きまわる「月」。飛びちがう惑星の軌道のような「雨」。くねくねの湧きつづける「地図」。もちろんこんな感じじゃない句もいっぱいあるんですが、でも何だろうこれ?と気になる程度には、飯島作品というのはぐちゅぐちゅ・ぐにゃぐにゃしている。いったいこうしたモチーフは、作者にとってどのような意味をもっているのか? それを整理するのが本稿の目的です。
2. 変質と生命
初めに引くのは熟成、発酵、腐熟、孵化、半熟などの〈熟=ぐちゅぐちゅ〉として世界の質感が描かれた例。
水孵るコンビニの灯を浴びながら
醗酵はセンサーライト浴びながら
仏蘭西の熟成しきった地図である
髭を剃るアボカド熟れているときも
饐えてゆく桃 うそはまだあるはずで
オムライスみんなこわくはないのかな
最初の三句は変質の発生から熟成まで、また後半の三句は後熟段階から死までが詠まれていますが、いずれにおいても作者が対象の変質にじっと感覚を研ぎ澄ましているのがわかります。とくに後半の「髭を剃るアボカド熟れているときも」「饐えてゆく桃 うそはまだあるはずで」 では、髭に刃をあてる光景やあるはずの噓といった予感が〈迫り来る死〉の記号として機能しているようす。また変成の完了した卵、すなわち生命そのものであるはずのものの全き死を怖がっているとおぼしき「オムライスみんなこわくはないのかな」は、作者の心境がはっきり書かれているという意味で貴重です。
飯島作品にとって「卵」とは何かについては、柳本々々にたいへん重要な考察〔*1〕が存在します。柳本氏は、飯島作品の言語空間における「オムライス」ないし「卵」とは「未生から生、あるいは生から死への変質」を表すモチーフでありかつ「生と死が交錯する〈生命〉をめぐる意味空間の生成装置」だと推論します。そしてその推論を「ナイフにて開く半熟オムライスまたは誰でも良かった犠牲者」というこの作者の短歌で裏打ちするのですが、柳本氏の「生と死が交錯する〈生命〉をめぐる意味空間の生成装置」なる見方は、卵のみならず〈熟=ぐちゅぐちゅ〉にまつわる変質一般に対する飯島作品の緊張感を説明するのにもぴったりです。
3. 逼迫する時間性
さらに柳本氏は「とおいとおいみらいをおもう箸先で卵の黄身をつついたりして」といった短歌を引いて「この歌で大事なのは『つついたりして』じゃないかとおもうんですね。〈つつく〉ということは、破裂・破砕のリスクがあるわけです。語り手はあえてつつくことで未知の時間を〈いま〉あふれさせようとしている。『とおいとおい』とはいいながらも、がまんしきれずに、逼迫する時間性がここにはある」と主張します。この主張もまた卵の枠を超えて、次のような作品を読み解く糸口にできそうです〔*2〕。
息止めていてくださいね羽化します
ああ、ああ、と少女羽音をもてあます
みじか夜の淫夢みるみる声変り
変声はコーヒー豆を落としつつ
梅雨の冷えかふかかふかと咳をする
これらは主として身体成熟という変質性をファンタスティックに描いた句ですが、「息止め」「ああ、ああ」「声変り」「変声」といった声帯描写は、大人という遠いはずの時空が「逼迫する時間性」として作中人物を襲うようすを非常にスムーズに演出しています。少しだけ解釈を挟むと、四句目「変声はコーヒー豆を落としつつ」における「コーヒー豆」は、おそらく焙煎が人工熟成といった変質性であることから導き出された語でしょう。また五句目「梅雨の冷えかふかかふかと咳をする」の「かふかかふか」はあからさまな「変身」の喩。梅雨冷えによる身体の変調が、語り手に自己のメタモルフォーゼを幻想させたのだと思われます。
4. 螺旋的起源へ
ところで卵というのは殻、半透明の薄皮、水っぽいゼリーなどで覆われたオブジェですが、こうした覆いすなわち〈境界〉を熟視したり破砕したりする衝動は、次の句群を見ても作者にとってかなり強烈です(ちなみにこの〈境界〉は水、硝子、鏡、窓、壁、障子、皮膚など、さまざまなヴァリエーションでもって飯島作品を満たしています)。
@みつ@@めなさ@@@@い胎まで
アメッシュに胎児の夢が映り出す
擦り硝子越しなる母と姉の腸【わた】
実母から伸びゆく錆びた螺旋階
「誰ですか」(落したのですDNA)
卵子、あるいはとぐろを巻くへその緒のような「@」の狭間に現れる、胎内を熟視しよとの命令。水膜の喩である「アメッシュ」に映る胎児、すなわち成熟中の生命の見る夢。磨り硝子の向こう側に見える、似かよった二本の腸。実母を突き破って伸びる、腐食した螺旋。DNAを探す誰か(おそらく身体以前の生命)とテレパシーで会話する語り手。このように作者が見尽くす〈境界〉の内部は、通常の生と死をめぐる〈熟=ぐちゅぐちゅ〉イメージをはるかにさかのぼり、生命の原型たるDNA二重螺旋すなわち〈捩=ぐにゃぐにゃ〉の領域にまで及んでゆきます。またこの延長上にあるのが次の二句。
うな底につがいとなれり双つの眼
浮いてたね鏡文字など見せ合って
ここでは「つがいとなった双つの眼」や「見せ合っている鏡文字」といった双生児性を際立たせる演出が、一対かつ二重なるDNAと同範のイメージを担いつつ、海底や浮界といった生命の起源的トポスを漂っています。さらに言うと、飯島章友にはこうしたイメージを全てひっくるめた 「シニフィアン/シニフィエ」という連作もあって、そこでは本稿で確認してきた要素がこの上なくオーガニックに息づいています。
シニフィアン・シニフィエ
雨催いくすりくすりとバナナ熟れ
文字盤のⅫが海であったころ
否と言うシニフィアン氏のうすいくちびる
時計草、否磔刑の男たち
手鏡の縁がとけゆく 雨ですね
蓮根の穴を墓場と決めている
残された骨を象形文字と呼ぶ
【詞書】蟬たちを拾ってあるく、そのような
九月生まれのぼくの天職 佐藤弓生
文字盤で蝉を育てるぼくの天職
九月の蝉を拾い集めるシニフィエ氏
くちびるは天地をむすぶ雲かしら
「雨催いくすりくすりとバナナ熟れ」の、今にも空を破ってあふれそうな雨催い=切迫する時間と、熟れるバナナ=変質のとりあわせ。「文字盤のⅫが海であったころ」「九月の蝉を拾い集めるシニフィエ氏」「文字盤で蝉を育てるぼくの天職」では、時間をつかさどる文字盤を生命のはじまるトポスとしての海に例え、そこで蝉という、おそろしいまでに熟成に似た生涯を送る生命を拾い集め、天職として飼育します。「時計草、否磔刑の男たち」の「時計草」はキリストの受難を象徴する花なので、そのまま〈未来のようにみえて実は逼迫する死の時〉の表象とみなすことができる。そして「否と言うシニフィアン氏のうすいくちびる」「くちびるは天地をむすぶ雲かしら」の、一対性および二重性を表象するくちびるのズームアップと、そのくちびるに危うく結ばれてる天地の星雲的質感。
ここへ来てこの連作最大の謎は「シニフィアン・シニフィエ」というタイトルの意味するところとなりました。私の考えでは、このタイトルは〈一対性/二重性/螺旋性〉を体現する〈言語という生命の二重螺旋モデル〉として作者がシニフィアン/シニフィエを捉えていることに由来します。またここから作中の「シニフィエ氏」と「シニフィアン氏」とが鏡合わせとなった一人の人物、すなわち「ぼく」であるといった予測も可能となるでしょう。
「ぼく」とは〈シニフィアン/意味するもの〉と〈シニフィエ/意味されるもの〉との〈捩れ〉に宿る存在です。また「手鏡の縁がとけゆく 雨ですね」と書かれる通り、自分の姿を覗き込む(熟視する)ときもその変質は止むことなく、つねに〈熟れ〉ゆくイメージに覆われた存在でもある。そんな「ぼく」の変質が止むのは、シニフィエ氏とシニフィアン氏の死んだあと「残された骨を象形文字と呼ぶ」ときなのかもしれません。
これが飯島章友ならではの世界を読者が追体験するのに恰好のテクストであるのは以上のとおりです。あらゆる対象への熟視に基づいた生命の風景。よじれとうごめきとが織りなすその蠱惑のたたずまい。こうした世界をかくも気品ある寓意と宇宙的な肉感とを共存させつつ描きつづける作者に対し、わたしは心から脱帽するものです〔*3〕。
註
〔*1〕柳本々々「こわい川柳 第七十二話」
http://yagimotomotomoto.blog.fc2.com/blog-entry-940.html
〔*2〕〔*3〕今回のエッセイの趣意を離れた場面においても〈生と死が交錯する意味空間の生成装置〉〈いまここにあふれそうになる未生の時間〉〈未来のようにみえて実は逼迫する時間性〉といった感覚をあつかう作品が飯島章友には多いようです。一例を挙げると、本文で引用した「とおいとおいみらいをおもう箸先で卵の黄身をつついたりして」のヴァリアシオンとおぼしき「〈戦争の放棄〉を守るわたくしは幸せの字を「死合せ」と書く」には〈しあわせ〉という言葉のもつ、いま述べた特色に加えて、生と死とのあいだの〈一対性/二重性/螺旋性〉にまで意識が及んだ典型的作品といえるでしょう。
Posted by wh at 0:06 0 comments
2017-01-01
【新春対談】〈身体vs文体〉のバックドロップ 格闘技と短詩型文学 小津夜景✕飯島章友
格闘技と短詩型文学
小津夜景✕飯島章友
はじまりはカンフー
飯島●小津夜景さんは2016年10月に句集『フラワーズ・カンフー』(ふらんす堂)を上梓されたばかりです。句集や歌集のタイトルに「カンフー」が使われている例をわたしは知りません。しかも、ただのカンフーではなく『フラワーズ・カンフー』ですからね。フラワーとカンフーの取り合わせには意表をつかれました。
 |
| Ozu Yakei ©saki irimajiri |
飯島●「ふわふわ山脈」「一人ゆらゆら大移動」もいいですね!
 |
| Iijima Akitomo |
小津●古館伊知郎ふうに実況すると「世阿弥の化身か、はたまた芭蕉か、侘びケ原の主戦場にゆらりと戦ぐフラワー・シンドローム、まさしくフラワーズ・カンフーです!」というブルース・トークになるのかしら。そこまで行っちゃうと、完全に興行ですね。
飯島●句集タイトルと同じ「フラワーズ・カンフー」という連作には、
教師三十六房僧と化し朧
という句があります。世代によってわかるひととわからないひとがいると思いますが、わたしなどはカンフー映画を子供の頃に観て育ちましたので、『少林寺三十六房』という映画を想起しました。日本公開は昭和58年です。
小津さんが武術に初めて興味をもったのは、やはりカンフーとか中国拳法とかそのあたりなんですか?
小津●はい、香港系のカンフー映画が最初です。サモ・ハン・キンポー率いる洪家班のコレオグラフィーが好きでした。
飯島●サモ・ハン・キンポーかあ。ジャッキー・チェン、サモ・ハン・キンポー、ユン・ピョウ、リー・リンチェー(ジェット・リー)、よく観たなあ。
句集には、
仁★義★礼★智★信★厳★勇★怪鳥音
という句もありますね。かつて『週刊少年サンデー』に連載されていた『拳児』を想います。
わたしは『拳児』自体はおぼろげな記憶しかないのですが、原作者で中国拳法研究家の松田隆智さんが書いた『謎の拳法を求めて』は思い出の一冊です。わたしとおなじ格闘技好きの友人が「読んでみろ」と強引に貸してくれて、しかも後日感想を聞かせろというもんだから、しぶしぶページを開いたんだけど、どうしてどうしてこれが面白いのなんの! 無我夢中になって読み進めました。
小津●松田隆智もわたしの原点ですね。彼の発行していた『武術』とか。たまに気が向くと「ひらけ!ポンキッキ」で放映していた彼の演武(楽曲『カンフー・レディー』のこと)をプロジェクターで壁に映しながら練習もします。
「動けるデブ」の躍動
小津●最盛期のサモハンの映画はラム・チェンインが中心となってカンフー・シーンの動作設計をしていたのですが、それが他の映画と比較してずば抜けて良いんですよ。『鬼打鬼』(1980年)のラスト・ファイトとか。
飯島●サモハンは「動けるデブ」として日本でもすごく人気がありましたよね。
小津●「動けるデブ」ってテクニカルタームなんですね。耳にはするけれど、まさか概念として存在するとは思っていませんでした。
でも考えてみると、お相撲さんってみんな「動けるデブ」……。
飯島●たとえば運動神経のいい巨漢のひとって走っても速いんですが、スピードが出るまでにけっこう時間がかかるんだとか。だからお相撲さんの瞬発力って驚異的なんですよ。われわれは見慣れてしまってるからあれですが。
小津●あのバネを思うと、うーん、やっぱりお相撲さんっていわゆる肥満じゃないのでしょうね。糖尿病とも無縁ですし。無差別級だから、吊り上げられないように脂肪をつけておこうって作戦かしら。アザラシみたいに。抱き上げにくそうですもんね。アザラシ。
飯島●1980年代、クラッシャー・ブラックウェルっていう180キロの巨漢レスラーがいたんですが、その人はその体重でドロップキックをしちゃうの。それだけで木戸銭が取れる。格闘技なんてわからないわたしの祖母もブラックウェルがドロップキックをすると大喜びしていました。
小津●あはは。愉しいおばあさま。
飯島●ラム・チェンインの動作設計と、サモハンの「動けるデブ」な身体能力。動けるデブばっか連呼するのも失礼な気がするけど、「動けるデブ」って誰が見てもわかる凄さ、娯楽性があると思うんです。
小津●なるほど。相撲の魅力の根っこも、案外そこにあるのかも。
飯島●相撲に「かわいがり」っていう一種の稽古がありますよね。以前テレビで観たことがあるのですが、30分以上、一人の若い力士相手に格上の力士が向かってこさせるんですね。当然途中で若い力士はへばっちゃうんだけど、それでも立ちあがって向かってこさせる。あれを見ると、やはり普通の肥満の人にはない持久力もあるんだなあと思いました。
小津●単なるデブ、じゃない。
飯島●子供のころ、実家にぶら下がり健康器(←昭和だ)があって、よくそれで懸垂をしていたんです。あるとき親戚のおじちゃんが「限界になってからが練習だ」と助言をくれました。極真空手に100人組手という荒行があります。1人の空手家が連続100人相手に組手をするんですが、当然ある人数を超えると限界が来るんですね。でもその限界を過ぎたところからが大切だと。
小津●たしかに。
飯島●いきなりレベルが格段に下がってしまい心苦しいんですが、『かばん』誌への歌を、まだ推敲できそうだけど今の自分じゃこれ以上無理だってところで提出しちゃうことがあるんです。でも翌日その歌を見てみると、難なく適切な言葉が嵌めこめて語順もすんなり改良できる。しもた~、あと一日早く作歌していれば!となる。上の限界を超える話題の文脈とつながっているかわかりませんが、歌作でそんなことが多いのを思い出しました。
小津●それは翌日だから発見できるのだと思います。いったん集中をリセットしているせいで。対象に執着しすぎると身体に〈居着き〉が起こって、かえって切り込む箇所が見えなくなる。それよりか適度にリラックスして、おしゃべりなんかしながら組み合った方が対象を捉えやすい。つまり知覚の判断を鈍らせないためには、気を上手に散らす工夫が大切なんですね。わたしは俳句の多作多捨も、気を分散させた状態での一点力を養う訓練だと考えています。
型の反復=ブルース・リー
小津●カンフーとのなれそめに話を戻すと、ラム・チェンインの存在が大きかった。彼の詠春拳の演武を見て、チャンスがあれば自分もやりたいと思ったり。詠春拳はブルース・リーの学んだ拳法でもありますし。
飯島●ブルース・リーといえば『燃えよドラゴン』(1973年)です。この作品、冒頭でサモハンが対戦相手の役をしているんですよね。二人とも今でいうオープンフィンガーグローブを付けて。
小津●うんうん。サモハン以外にも、のちの香港映画界を支える役者がひしめいている。リーのバク転の代役をユン・ワーが務めていたり、ラスト・ファイトの敵の代役がラム・チェンインだったり。みんなまだ20歳そこそこなのに。
そういえば、この映画のメイキング・フィルムにブルース・リーが棒術アクションの動作設計をしているシーンがありまして、それを見ると彼、棒術のはじめに学ぶ2、3の基本動作だけで殺陣を組み立てているんです。拍子抜けするほど特別なことはしていない。でも体捌きが綺麗だから説得力がある。踊っているようにすら感じられてすごい。
飯島●「基本動作なのに綺麗で踊っているようにすら感じられる」……なるほどねえ。それはおそらくブルース・リーが来る日も来る日も「型」の反復練習を行ってきて、「実」がしっかりしているからではないでしょうか。型というと悪いイメージと良いイメージがあって、悪い方だと「型にはまっている」「よくあるパターンで既視感がある」なんていわれることがあります。逆に良い方だと「彼は型を持っている」「形がぶれず軸が安定している」なんてね。
小津●ええ、言われますね。
飯島●型の悪い面というのは、いつしか伝習になって硬直化・形骸化してしまい、日々の有機的な移り変わりに対応できなくなることなんだと思います。でも逆に良い面というのもすごくある。ものごとをどうやったら効率よく合理的に行うかということの知恵、何といいますか、先人の試行錯誤という篩にかけられた合理的技術の凝縮ですね、そういう面があるんではないでしょうか。
で、それを何千回といわず何万回といわず反復して身につける。そうすると無駄なものは削ぎ落とされる。なので、かたちに美しさがあらわれる。茶道でも華道でも武道でも、あるいは短詩型文学でも何でもいいんですが、型には美しさが感じられます。
プロレスの型と短詩の型
飯島●基本動作がしっかりした人は、「実」という基本を「華」として美しく見せられる。自由自在です。これはプロレスリングでもまったく同じだと思っています。
小津●「実」という基本を「華」として美しく見せるプロレス……。なんだかロラン・バルトの『神話作用』を思い出します。
飯島●ロラン・バルトですか。バルトといえばわたしの家のパソコン、barutoと打ち込んで変換すると「把瑠都」がいちばん最初に出てくる。元大関の把瑠都ですよおぉぉ!!!
小津●それはまた業の深い……。
飯島●わたしはフランスの思想家に疎いのですが、ロラン・バルトはむかし読んだことがあります。
小津●『神話作用』は現代フランスの日常にひそむ"神話的事象"についてのサブカル・エッセイ集ですが、その記念すべき第一節が「レッスルする世界」というタイトルの、今や古典となったプロレス論(1954年発表)です。そこでバルトはプロレスの良さを、マスクやら高下駄やらを含めて〈古典演劇と同種の誇張された見世物であること〉とし〈感性、儀礼による芸術形式〉と定義しています。
飯島●バルトの前提は正直非常にリスクを伴う論だと思うんです。
小津●彼って「はたしてプロレスは演技か競技か?」といった、この世に実在する熾烈なイデオロギー闘争をあっさり無視していますもんね。
飯島●ただプロレス、ひいていえば格闘技が古来からもつ儀礼性一般についてとても重要な指摘をしていたと思います。
小津●「レッスルする世界」にはこんなことが書いてあります。
観客が求めるのは、情熱のイメージであって、情熱それ自体ではない。レスリングにおいては、劇場においてと同様、真実という問題はないのだ。どちらの場合でも、期待されているのは、通常は秘密である精神的状況のわかり易い形象化である。この、外的表象のために内面をからにすること、形式によって内面を汲み尽すことは、正に勝ち誇る古典芸術の原理である。こうした内面に還元されることのない〈身ぶり〉、すなわち「実たる型が、すなわち華だ」という発想は短詩の型でも見られます。わたしは万葉集の巻頭を飾る雄略天皇の求婚歌、
〈身ぶり〉はすべての余分な意味を切り払い、観衆に対して儀礼的に、自然と同じようにきっちりした、純粋で充実した意味を提供する。
籠(こ)もよ み籠持ちが大好きなのですが、これってすごくプロレスに似た〈他者への儀礼性〉や〈誇張された見世物の力学〉を感じさせると思いません? こう言うとなんですけど、古館さんの前口上みたい。
掘串(ふくし)もよ み掘串持ち
この丘に 菜摘(なつ)ます子
家告(の)らせ 名告らさね
そらみつ 大和の國は
おしなべて われこそ居(を)れ
しきなべて われこそ座(ま)せ
われこそは 告らめ 家をも名をも
またさきほど飯島さんが言及なさった〈型〉の長所および短所を『神話作用』に絡めるなら、バルトは「プロレスのルールはルールそれ自体を乗り越えるために存在する」と言いますよね。
正義は故に、有り得べき違反の総体である。法を乗り越える情熱の光景は何よりも価値があるという法則があるのだ。ルールはやぶられるためにある、という転倒。カーニバルの論理。型の中に生きることの醍醐味はたぶんこれに尽きるでしょう。型というのは決して微温的な閉鎖空間ではない。むしろそれがいつ転倒するかもしれないリングに遊ぶ機知、すなわち「レッスルする世界」を生きる歓びをもたらす装置だと思います。
プロレスに詳しい飯島さんにとって〈プロレスリングの型〉と〈短詩の型〉との類似性はどういった点になりますか?
飯島●はじめに申し上げておくと、プロレスリングというのは時代、団体、国、選手個人によって、てんでばらばらなジャンルなんです。たとえばです、かりに一本の横線があったとしましょう。その横線の最も右端には桜庭和志、田村潔司、ダン・スバーン、ジョシュ・バーネットといったレスラーがいます。総合格闘〈競技〉で大活躍し、なおかつサブミッションホールド(関節技・絞め技・Hook)もマスター級の選手たちですね。むかしのレスラーでいえばダニー・ホッジは間違いなくここに入るでしょう。
小津●ダニー・ホッジかあ……。そういえば、まだ西東三鬼のことを何も知らなかったころ、「露人ワシコフ叫びて石榴打ち落す」の「ワシコフ」はプロレスラーなんだと信じきっていました。YOUTUBEで「殺人狂コワルスキー&地獄の料理人シュミット」の試合を観たことがあったせいで。ごめんなさい。だから何って話でしたね。つづけてください。
飯島●あははっ。コワルスキーvsシュミットを観ようなんて人は、小津さんと同世代にはたぶんいませんよ、このわたしを除いてね。話を戻しますね。反対にロラン・バルトがいうような〈儀礼的〉にレスリングを行うレスラーは最も左端に位置します。平成でいえば大仁田厚。ソ連のアマチュアレスリングの強豪がプロレスラーに転向してきたり、競技性を前面に打ち出すUWFスタイルが一般社会でも注目されていたなか、彼は自覚的に見世物としてのプロレスを再浮上させたひとです。大仁田の師匠だった馬場さんも晩年はそうでしたよね。プロレスの儀礼的な側面をパロディ化して、みんなが楽しんじゃうところまでやり続けた。
小津●大仁田厚の登場がルネッサンスだったのは肌で感じました。とても明快なデスマッチ。
飯島●感情の表し方も凄かった。で、そうするとね、バルトは最も左端のレスラーに焦点をあててプロレスを定義しているんですよ。これはわりと簡単なんです。なぜといって、左端だったら「通常は秘密である精神的状況のわかりやすい形象化である」でしょう。右端だったら勝つか負けるか、強いか弱いかでしょ。でもね、今はどうか知らないけど昔ながらのプロレスファンってのは、格闘技が古くから担ってきた「儀礼性」と、法治・自由意志に基づいた近代的な「競技性」、この両側面の葛藤・逆説・矛盾・二律背反を引き受けていたんです。そして或るエステティックな手応え、境地を探し続けていたんだと思いますよ。
小津●たしかにプロレスファンというのは美学的ですよね。おのれの感性と悟性との交渉を試みる場として、リングでの出来事を吟味している。
飯島●うんうん。先ほど小津さんがいわれた〈型〉に話をつなげていくために、ここでちょっとプロレスリングの歴史について話をさせてください。19世紀後半から発展した近代プロレスリングは近代的な競技性と古くからの儀礼性、この二側面が混在したジャンルだとわたしは考えています。「キャッチ・アズ・キャッチ・キャン」スタイル、「グレコローマン」スタイル、「カラー・アンド・エルボー」スタイルという〈競技〉レスリングと、カーニバル・レスリングといういかがわしさ満載の〈見世物〉が合わさり、現在のプロレスリングの原型が出来たということです。
小津●すごくわかりやすい!
飯島●プロレスリングの見方は当然ひとそれぞれだけど、ぼくは「プロレスとはこういうものだ」っていう前提はもたないようにしたいんです。ぼくがプロレスリングに魅力を感じるのは勝負と儀礼、言いかえれば〈私闘領域〉と〈儀礼領域〉の往還を試合のなかに嗅ぎ取ったときなのです。ここでいう私闘領域ってのは「キャッチ・アズ・キャッチ・キャン」スタイルの遺伝子、そして儀礼領域ってのはカーニバル・レスリングの遺伝子が顔を出したとき……な~んてなこと言ったりなんかしちゃってね、ちょっとかっこ良すぎかな。
小津●いまのお話、わたしの視点から少し補足しますと、近代に国民国家が誕生するにあたり徹底された法律のひとつに〈決闘の禁止〉というのがありました。これは国家が暴力を独占するための政策で、この法律以前は命を賭けた殺し合いは悪ではなくむしろ一種の高潔さとして考えられていた。イギリスには騎士道なんてのもありましたよね。
で、決闘という文化はこうした法制化の過程で社会から完全に消滅したのかというと実はそうではなく、近代的私闘としてリングの上に再表象化されたという風にも言えますね。
飯島●力道山が初めてルー・テーズと試合をしたのは1953年、ホノルルです。テーズは当時の世界王者で、とうぜん観客論をわきまえているのですが、格闘家としても超一流。飛行機のない大正時代にわざわざ来日し、日本柔道に挑戦状を叩きつけたアド・サンテルというレスラーの弟子なんです。アド・サンテルは、まあ言ってみれば「逆前田光世」ですな。
で、テーズが言うには、試合開始の直後、力道山が狂ったように頭突きの連打をしてきたのだと。テーズも報復として左ストレートを力道山の顎にお見舞い。なものだからレフェリーが二人をなだめて頭をクールダウンさせたというのです。
要するに、このときの攻防はお客様にお見せできるものではないということ。戦後のプロレスは競技とは違いますが、二人は近代社会で許容される枠を越えてしまったのだと思います。
小津●飯島さんのお話を聞いていたら、なんだかプロレスって凄いもののような気がしてきました。
わたしが武術に関して残念に思うのは、戦後もまだまだ拉致&殺人の術として盛んに活用されていたにもかかわらず、まるで昔から平和的・思索的であったかのように美化されすぎていることなんです。武術をプロレスよりも高尚だと思っている人も珍しくないですし。
でも飯島さんのエレガントな要約によれば、プロレスは勝負と儀礼すなわち〈私闘領域〉と〈儀礼領域〉との交差する場で葛藤を重ねてきた一方、武術は「殺の技術」としての歴史への無関心と、「生の技術」すなわち修身的な側面への自己賞賛とのアンバランスがあまりに酷い……。伝統文化に付随しがちなエリート主義がそうさせるのでしょうけれど。
「空っぽのこころ」という究極
小津●ところで、競技化された格闘技に私闘の匂いを嗅ぐというのは典型的な倒錯です。ルールという縄でリングをぐるぐる囲った上で、その隙間にちらちら見え隠れするナマの暴力に欲情するということだから。場外乱闘にしても、場内のルールがあってこその享楽。これは通常のエロティシズムと全く同じ構造で、リアルすぎる暴力というのは直視できないか、こちらを無感覚に陥らせるかのどちらかになってしまう以上、パブリックな部分とプライベートの部分は絶妙にせめぎあっている必要がある。このせめぎあいのじらしにハマる人がたくさんいそうです。
飯島●先ほどの〈型〉ということにつなげるならば、厳格な〈型〉にのっとって行われる儀礼のなかにおいて私闘を出さずにいられない試み。それは短歌にもあるような気がします。
聖母像ばかりならべてある美術館の出口につづく火薬庫 塚本邦雄
句またがりによる〈型〉と〈私〉のせめぎ合い。新しい律の試み。プロレスでいうと観客席とリングの間にマットが敷いてあるところ、いわゆる〈場外〉ですね、あそこで戦うことも許されるようになった感じでしょうか。
特急券を落としたのです(お荷物は?)ブリキで焼いたカステイラです 東直子
この丸括弧は、プロレスでいえば〈乱入〉みたいなものかな。
小津●まさか句またがりが〈場外〉だったとは。東直子の〈乱入〉的手法も、一人称文学だと思われている短歌においてラディカルな意義がありそうですね。
飯島●と、思います。
小津●プロレスから武術へと話は逸れますが、わたし、武術の型というのは儀礼として極まってしまうと私闘の介入する余地がなくなる気がするんです。
たとえば暴力に私情を交えないのが建前という意味で儀礼的行動がもっとも徹底されている(ことになっている)のは軍隊ですが、これについて考えるとき、いつも『酔拳』でジャッキー・チェンの敵役を演じた黄正利のことを思い出すんですよ。黄は知る人ぞ知るテコンドーの達人で、ヴェトナム戦争のときは現地教官として米軍からの招聘を受けたほどの腕前なんです。
飯島●『酔拳』と『蛇拳』はテレビの再放送で何回も観ているのですが、髭をはやしたあの敵役のひとにはそんな経歴があったんですか。
小津●ええ。ところがある日の教練中、武術など実戦で役立つものかと馬鹿にした軍人が彼を背後からナイフで襲撃する事件が起こった。で、そのとき黄はどんな行動をとったのかというと、その殺気を背中で察し、ふりむきざまに相手を一蹴で瞬殺しました。
飯島●伊東一刀斎の夢想剣みたいだ! 戦国~江戸初期の剣豪だった一刀斎は、あるとき不意に襲ってきた敵の殺気を無意識のうちに察して斬ったといいます。続きを聞かせてください。
小津●周りにいた軍人たちが100%正当防衛だったことを証言したおかげで彼は無罪になったのですが、今はとりあえず〈無罪/有罪〉とか〈善/悪〉といった話は一切忘れてですね、確認したいのは武術とはこういうものだ、ということ。黄正利は生きるか死ぬかの極限状態において武術をしかるべく使用した。
このエピソードを知った時、武術において〈型という儀礼〉を極めた場合、そこに現れるのは一切の人間らしさを寄せつけない「空っぽのこころ」という〈究極の型〉になるのだな、と思いました。またこの大前提に立った上で、武術家たちは如何にこの血も涙もない場所から〈究極の型〉を救出するかを模索している……
飯島●学者さんたちが〈儀礼〉という言葉を使い、格闘技が担ってきた機能を説明することがあります。そこでは子猫のじゃれ合い、部族間の和解、敗者の従順の証し、神への奉納といろんな例が出され、調停システムとしての〈儀礼〉が説明されます。でも小津さんのいう〈儀礼〉や〈究極の型〉というのは格闘技のそれではなく、生き死にから救出される〈武術〉のそれなんですね。
小津●わあ……整理してくださってありがとうございます! いまちょうどね、言葉が考えを追い越してしまって自分の話が自分にも謎だったので、すごく助かりました。そうです、飯島さんのおっしゃるとおり格闘技の儀礼は調停システム、すなわち〈自己と他者のコミュニケーション論〉の次元で説明されることがもっぱらです。いっぽうわたしはそれを〈生と死のコミュニケーション論〉という次元で語ろうとしていた。で、それによって生と死の二元論を超えてしまった…
飯島●「空っぽのこころ」。〈究極の型〉……。
小津●そう。もはや人間の尺度では測れない世界に行ってしまう。でね、わたし、この「空っぽ」が虚無なのか充溢なのかは決定できないと思うんです。心の中ではその両方の可能性が重なりあっていて、それこそシュレーディンガーの猫のように開けてみるまでわからない。愛と殺、生と死、エロスとタナトスといった可能性がつねに混交している。
飯島●すこし話が煩雑になってきましたので、大雑把にこれまでの文脈をたどると、実践=実における〈型〉の話から、その〈型〉を華としても見せられるブル―ス・リーやプロレスの〈儀礼〉性へと話が移りました。
映画や格闘技での〈儀礼〉は基本的に死にはつながらず、むしろ〈調停システム〉として生を謳歌するところへもつながります。
ところが先ほど小津さんは血も涙もない過酷な状況を前提にした分野、つまり武術を出してこられた。そのとき問題になってくるのが、生と死の二元論を超えた「空っぽのこころ」、いわば心的な〈究極の型〉とは何ぞやということですね。
小津さんはその次元が虚無になるか充溢になるかの対立項ではなく、愛と殺、生と死、そういうものがカオスの状態になっている、と。
「我」と「敵」をめぐる弁証法
飯島●「無敵」という言葉がありますね。あれは武道的にいうと「我が無いから敵も無い」という究極の強さのこと、とたまに聞きます。『燃えよドラゴン』の中で主役のリーが喧嘩を売られるシーンがありますよね、船上で。
相手から流派を訊かれたとき「戦わずして勝つ芸術さ」と返答するんです。仔細は省きますが、ここでリーは本当に敵と戦わずに勝ってしまいます。でも先ほど小津さんは、「空っぽのこころ」が虚無なのか充溢なのかは決定できないとおっしゃいました。してみると「我が無いから敵も無い」という理想はなかなか厄介な境地かもしれないぜ、ということになりますか?
小津●はい。冷静に考えると、「我と敵」をめぐる弁証法の彼岸に平安という悟りがあるとするのはかなり怪しい。だって仮に人間が〈死の欲動〉をもつという前提に立てば、二元論のフレームを脱出した瞬間、平安ではなく過剰性の方向へ突っ走ったっておかしくないもの。
この〈死の欲動〉というのは割に誤解されている概念ですが、ジジェクが「決して破壊されないものになる享楽」と説明するように〈死に向かう衝動〉ではなく〈不死への駆り立て〉なんですね。終わりある存在から終わりなき存在への飛翔。バタイユの考えるエロティシズムに似ているかも。我彼の箍を外す小さな死、とか。
飯島●理性による弁証法の果てに全体主義体制が現出したと私は思っています。人間理性が不完全だからです。その意味で人間の未来は不確実であり、理想的状態を導き出せたこともないし、至ったこともない。でもそれでいいと思う。「行」を通じて血や恥が「知」になるよう努めていく終わりなき存在……それが人間という気もします。
さて専門的な用語も出てきましたが、要するにこういうことでしょうか。〈死の欲動〉というのは……人間も最初は生命を持たない無機物だったわけだけど、あるときいきなり生命が宿ってしまったことで緊張が生じる。その緊張を解消しようと思って生命の無い最初の状態に戻ろうと欲する。確かこれが〈死の欲動〉だったでしょうか。
で、この〈死の欲動〉は言ってみれば破壊本能です。本能だから容易に消せるようなものじゃないぞ、と。したがって下手に我と敵、つまり自他の区別が解消されてしまったら見境のない攻撃性が生じてしまう懸念もある……という感じでしょうか? だとするとやはり「空っぽのこころ」とは……。
小津●結局「空っぽのこころ」という〈究極の型〉を血も涙もない場所から救出するためには、その型の縁ぎりぎりに立つしかないのかもしれません。限界まで〈究極の型〉に近づきつつも、決して私を手放さない、というような。
〈究極の型〉から〈型の溶解〉へ
小津●現実的な話、「戦わずして勝つ芸術」ができる無敵の達人って、実は無我じゃないですよね。みんなが思うような空っぽじゃない。〈究極の型〉におのれを預けてしまえば己が鬼になると知っているから、いつでもその型の縁すれすれで、ゆらゆらしている。
飯島●なるほど! 形而上の平安を安易に持ち出すのではなく、あくまでも実存的な姿勢を離れないのですね。そういえば鎌倉時代に日本曹洞宗をひらいた道元などは、無っていうのは目指すものではなく自分自身が無だというのを悟ることだ、と『正法眼蔵』現成公案の巻に書いていたと思います。
小津●わたしね、詩歌の世界でそれをラディカルにやると、型がトリック・アート的に溶解することになるのでは、と思うんです。例えば、
いましがた姉にあねもねいま胸にわすれもしねえむねえもしゅねえ 小池純代
この作品は、無我無心に似た言葉のふるまいが、型の縁をかすませたように感じられます。あるいは、
静かなうしろ紙の木紙の木の林 阿部完市
この句は、しずかな後ろで紙と木といった質料と形相がくるくる回転するうちに、型が錯視的に消されてしまっている。
飯島●上五が7音で、そのあと句またがりをして「紙の木」が反復される。おっしゃるようにくるくる回るような不思議な感覚になってきます。阿部完市の俳句と重なるところがあるかはわかりませんが、川柳にもこういう句があるのを思い出しました。
らららなのはな春はすくらんぶるえっぐ 内田真理子
内田さんには他に、
イツカワタクシヲタベツクスコトバ
という川柳もあります。「言葉」ならぬ「コトバ」に食べつくされてしまうという想い。「言葉」というものは歴史を背負っています。
言葉を用いるときはその歴史の文脈のなかで発展してきた〈型〉、いってみれば予めの慣用があります。後期のヴィトゲンシュタインも「語の意味とは言語内におけるその使用」なんだといっていました。
でも反対に「コトバ」といった場合、それは型をもたないのでしょう。型のないところでは不安も出てくる。コトバに遊ぶ者の恍惚と不安、そんな感じを受ける句です。
小津●カタカナ表記が、人間に捉えがたい異界を演出しているのですね。その上で、私が言葉を欲望していたはずが、いつのまにか言葉が私を欲望していたという「コトバに遊ぶ者の恍惚と不安」を語っている、と。
あと「言葉」が「コトバ」になっただけでなく「私」も「ワタクシ」になってしまっている。型もなければ自己もない。さらに食べ尽くすということでお互いが溶解している。この句には、生と死、愛と殺、エロスとタナトスなどが対立項ではなく混交するものだということが描かれている気がします。
私闘と〈私〉性
小津●あらゆる格闘技は儀礼と私闘といった二つの領域にまたがるがゆえに二律背反を内包するわけですが、このことの確認は「俳句の型のなかでどのように書くか」を考える上でもたいへん参考になりますね。大切なのは、このアンチノミーを第三の項によって解決しようとせず、ふたつの原理のあいだで揺れていること。ふたつの原理の相互リアクションをじっと味わいつつ、矛盾と生きる姿勢。そういったメンタルコンディションを保つことだと思いました。
それにしても、実はわたし、今まで格闘技全般と短詩の共通項どころか、それぞれの性質についてまったく考えたことがなかったんです。だから今日の対談もだいじょうぶかしらと心配していたのですが、さいわい飯島さんに導かれました。すごく霧が晴れたというか、なんだかカウンセリングを受けた気分です。
飯島●短詩型文学という儀礼のなかにどのようなかたちで私闘、つまり〈私〉性が反映されてくるのかという問題は、プロレスリングを参照するといろいろ示唆されるもんだなと今回気づかされました。あと小津さんがお話になった武術の〈生と死のコミュニケーション論〉ね。あれも境涯詠とか社会詠に向き合うときの手助けになりそうです。要するに、そういう深刻なテーマに対峙しても出来るだけメンタルコンディションを保つということ。ちょうど格闘技の観客が、一見、戦いに熱狂しながらもオプティミストであるようにね。
あと小津さんとお話をさせていただきながら、短詩の型っていうのは五七五や五七五七七のことではないかもしれない、と思いはじめました。定型というのはあくまでも柔道とかプロレスの試合場みたいなものではないのかと。
ついでにいうと季語っていうのは柔道とかサンボの道着に当たるもので、それを着ていないのが川柳といえるかもしれない。だから川柳人はプロレスラーみたいなもので、正統派もいるけどブルファイターや凶悪ファイター、はては覆面レスラーまでいて、レフェリーのブラインドをついた攻撃をしようとする。次にまた機会があるのならぜひ小津さんの血性、いえ知性をお借りしながらこういうところもお話できたらと思います。今回はとても面白かったです。ありがとうございました。
Posted by wh at 0:08 0 comments
2016-09-04
【週俳7月の俳句川柳その他を読む】何度も反す八月の砂時計 2 飯島章友
【週俳7月の俳句川柳その他を読む】
何度も反す八月の砂時計 2
飯島章友
乾きの香忍ぶアブの死彼の際か 井口吾郎
連作「椅子」は回文です。回文は、上から読んでも下から読んでもおなじ音になることが要請される。だから、〈意味する〉ことと〈意味しない〉ことのせめぎ合いのすえ生まれるのが回文、といえます。したがって回文には、意味のせめぎ合いを経た緊張感がある。ことに上掲句は、「乾きの香」「忍ぶアブの死」という措辞の良さもあって、回文特有の緊張感が最もよくあらわれた一句だと思います。
「田中は意味しない」 福田若之
連作「田中は意味しない」は難しく、全体を整合化するのは私の手に余ります。ただ、何度か当連作を読み返していくなかで、心に浮かんだよしなし事をメモするくらいはできました。無理に整合化することはよして、今回はそのメモを記すに留めようと思います。雑なメモでしたので、文章の体裁だけはいちおう整えました。
●タイトルの「田中は意味しない」。面白いのは、「田中は意味しない」と言語化した時点で「田中は意味しない」、という意味が生じていることだ。語り手は、抽象的な〈私〉を立ててこの世界の外側に置き、それを認識主体にして「田中は意味しない」と田中を意味づけているようだ。このとき、語り手と田中には〈主・客〉の関係ができている。
●眼は眼を見ず、という言葉がある。眼は対象物を見る部位だが、眼自身を見ることはできない。眼自身も見られるなら、眼は対象物を見ることができない。だから眼というのは、〈見ない〉という自己否定をとおして〈見る〉作用を全うし、眼として機能することができる。
●「意味しない」は、〈意味しなくない=意味する〉という自己否定をとおして「意味しない」を成就する。この矛盾的な在り方を構文にすると、〈AはAでなくしてA〉となる。当連作にあてはめると、〈田中は田中でなくして田中〉だといえる。
●表裏一体という言葉がある。〈コインの表〉を例にすれば、それは〈コインの裏〉と背中合わせでなければ存在できない。同じことは〈コインの裏〉についてもいえる。そして、この〈表/裏〉という二重構造を〈表=裏〉として一体化させているのは、コインという〈場〉である。
●九句目「呼べば去りしらさぎは田中でなくなる」は、「田中は意味しない」という前提をふまえて言い換えるなら、〈呼べば去りしらさぎは意味してしまう〉となる。〈しらさぎは意味してしまう〉ということは、語り手としらさぎの間に〈主・客〉の関係が成立していることになる。もういちど〈AはAでなくしてA〉という在り方と、その在り方を支える〈場〉に戻って考えると、何か気づけるかもしれない。
虻は宙に停まれり蓮の真上なる 西原天気
季語として五月みどりの遍在をつくづく思ふ蒲田駅前 同上
「かの夏を想へ」は、俳句と短歌がワンセットになった連作。先行する自作歌から発想して俳句が附けられたようです。上掲の句歌のセットでは、「蒲田」→「(蓮田の)蓮」という道筋が想像できます。
最大の見どころは季語としての「五月みどり」。フラワーしげるさんの短歌に、「きみが十一月だったのか、そういうと、十一月は少しわらった」(『ビットとデシベル』)があり、ここでは「十一月」があたかも擬人化されて用いられています。上掲歌の「五月みどり」も、「五月みどり」という固有名詞から固有性が抜き取られ、解体されたうえ、あらためて季語化される面白さがあります。
ひとつ思ったのは、短歌は三十一音もの長さがあって便利だなあ、ということ。かりに「蒲田駅五月みどりが偏在し」という川柳があったばあい、現代川柳に馴染みのない読者からすると、「五月みどりの偏在?ん?ん?」と混乱する可能性もあります。それが短歌のばあい、「季語として五月みどりの偏在」なのだと前置きできる長さがあるのです。
戦争と三愛ビルの水着かな 同上
四角くて丸い世界の中心に馬場正平がゐた熱帯夜 同上
「三愛ビル」は戦後間もない昭和21年、銀座に建設され、当初は食糧品や文房具品が売られていました。それが昭和25年には婦人服専門店に変わり、昭和30年からは水着の販売が開始されます。そして昭和38年には、総ガラス張りの円筒形ビル「三愛ドリームセンター」としてリニューアルオープンしました。以降、銀座の名所のひとつとなっています。
いっぽう「馬場正平」は、プロレスラー・ジャイアント馬場の本名。「四角くて丸い世界」「馬場正平」「熱帯夜」というキーワードから考えるに、上掲歌は、昭和42年8月14日に大阪球場特設リングで行われたジャイアント馬場vsジン・キニスキーのインターナショナル・ヘビー級選手権試合と思われます。二万人の大観衆を集め、60分3本勝負で行われたこの試合は、1─1のイーブンのままフルタイム戦いぬき、延長5分でも決着がつかなかったジャイアント馬場の代表的な死闘。当日、すぐ近くの大阪府立体育会館では、ヒロマツダをエースとする国際プロレスも試合を行っていて、興行戦争の背景もありました。〝プロレス大坂夏の陣〟です。
「戦争」と「(死力を尽くした)試合」と「興行戦争」、「8月15日」と「8月14日」と「世界の中心に馬場正平」、「(戦後復興の現れとしての)水着」と「(高度成長期の娯楽としての)プロレス」、その他もろもろが響き合うことで、ゼロから発展した時代のムードが立ちあがってきます。ただし、この時代を実際に体験した人と、私のように知識としてしか知らない者とでは、表象の質は違ったものになるでしょう。
連作「かの夏を想へ」には、何十年というスパンがあります。戦後すぐの「徳川夢声」「三愛ビル」「笠置シヅ子」から、2015年のドラマ「釣りバカ日誌」にも出てきた「デルのパソコン」。また、連作の始めと終わりには「菅井きん」という、戦後長らく活躍してきた叙情的人名が配されてもいます。このため、作中主体のイメージは自然に立ちあがり、その作中主体をつうじて戦後日本人の喜怒哀楽が感得できます。昭和マニアの私にはたまらない連作でした。徳川夢声やトニー谷、谷啓など逐一語ってみたいのですが、俳句鑑賞の場なのでやめておきましょう。
梅雨晴や歩けば戦ぐ象の耳 村田 篠
梅雨は、「象」も屋内に入っている時間が長いことでしょう。そんな時季だからこそ、「梅雨晴」という季語が、「戦ぐ象の耳」という動態をしっかり支えています。と同時に、「梅雨晴」は、「歩けば戦ぐ」といった当たり前の現象に新鮮な味わいを与えてくれているようです。
列の崩れて湧水に触れてゆく 同上
何となく、窪田空穂の短歌「湧きいづる泉の水の盛りあがりくづるとすれやなほ盛りあがる」(『泉のほとり』)が思われます。「列の崩れて」のあとに意表をついて「湧水」が現れ、列の崩れは湧き水に触れるためだと分かる。場面を動的に描きつつ、しかしけっして大振りな表現にならぬよう言葉が展開していく。そこに、空穂の歌との連絡を感じたのかもしれません。
血のやうな大きな車夏の雨 上田信治
初読のとき、上五の「血のやうな」が「車」につながっていかず、一足飛びに「夏の雨」のほうへつながっていきました。「血のやうな大きな車」よりも「血のやうな夏の雨」のほうが、私個人の感覚には自然だったのです。いわば「血のやうな(大きな車)夏の雨」というイメージ。火矢のように荒々しく降り注ぐ「血のやうな」夕立のなか、雨に打たれるまま停留する「大きな車」。粗く、独善的な、初読らしい読み方に違いありません。それにもかかわらず、なぜか自分としては捨てきれない読み方なのです。
夏団地夕方いつかゴム臭く 同上
連作「夏団地」には、昭和の団地のイメージがあります。かりに今の団地だとしても、築何十年という古い団地に思えます。現在の都市部のマンションは、行き届いた管理のため無味無臭になっています。それに比べて昭和の団地というのは、表面的には平穏で整然としていても、生活の生々しさと怪しさが入り混じった雰囲気がありました。
上掲句、夏の団地が「夕方いつかゴム臭」いと。どことなく不穏で小気味悪い雰囲気。しかし、何かしっくりくるところもある。
――夕方の夏団地とはそういうものでございましょう。
そんな声とともに疑似的な記憶が呼び覚まされてくるのです。
Posted by wh at 0:03 0 comments
2016-08-28
【週俳7月の俳句川柳その他を読む】何度も反す八月の砂時計 1 飯島章友
【週俳7月の俳句川柳その他を読む】
何度も反す八月の砂時計 1
飯島章友
砂時計のくびれを落つる蛍かな 遠藤由樹子
この砂時計のなかに入っているのは、砂ではなく「蛍」の群れ。砂時計を逆さまにすると蛍は「くびれ」の上に凝集し、光の尾を引きながら少しずつ落ちてゆく。末尾「かな」の余情の効果で、果敢なさも帯びた幽雅な情景を心地よく受け取りました。
眠る子にプールの匂ひかすかなり 同上
あまりにも有り触れているため、普段の生活では特別気にもとめない場景かもしれません。けれど、定型とは凄いもの。こうして五七五にパッケージされただけで眠る子の愛しさ、その子の成長を見守る幸せ、そして平穏無事な夏を過ごしている充実感──そんなさまざまな感慨がじんわりと伝わってきました。戦後社会では、〈限定〉が負価値として捉えられてきた面もあるかと思います。けれど、私はこのような作品に触れるたび、〈限定〉することの素晴らしさを思わずにいられません。
揚羽蝶連れて飛び石渡りけり 同上
「飛び石」を渡っているときにたまたま「揚羽蝶」と移動が重なった。ちょっとした巡り合わせである。でも通常ならば、飛び石を渡り切って一分もしないうちに忘れてしまうレベルのことかもしれません。それが、ひとたびこうして五七五にパッケージされただけで、揚羽蝶との巡り合わせをいつでも再生できる。これも〈限定〉による効果といえるでしょう。
シーソーに一人は静か夏の空 同上
シーソーに一人で腰をおろしたときの静けさ。その静けさが、複数人と興じるシーソー遊びで見過ごしてきた「夏の空」を意識させた。〈静〉を得たことによる発見といえるでしょう。と同時に、普段の忙しない〈動〉としての〈私〉を上から支えていたのもこの「夏の空」だった、と気づいたのではないでしょうか。
ところで上記までの読みは、一句単独を前提としてのものです。近代以降の短詩では、八作品なり十作品なりのパックで発表されることが多いので、多かれ少なかれ他の句が影響を及ぼしてきます。「夏の空」十句もそう。通しで読むと、〈生〉と〈死〉のコントラストがそこはかとなく伝わってきます。たとえば、「昼顔や孵りたてなる雛の嘴」「青柿も実梅もわれも雨の中」「目凝らせば梅雨の燕のかく高く」などは〈生〉を描いた句です。いっぽう、「みづうみに向く籐椅子の遺品めき」「花鬼灯喪服の傘のとりどりに」は〈死〉が関わっています。それに気づいたとき、掲出の四句が一句単独のときとは違う雰囲気を醸してきたから不思議です。まるで四句とも〈生〉と〈死〉のあわいが詠まれているみたいで。
風鈴と冷やし毛皮を売り歩く 竹井紫乙
毛皮の機能を転倒させた「冷やし毛皮」。その造語だけでも面白いですが、夏の風物詩とばかりに「冷やし毛皮を売り歩く」というのですから、リアルすら感じます。螢売、金魚売、風鈴売、そして冷やし毛皮売。
人でなし人面鳥に告げられる 同上
人間の顔をもつ「人面鳥」。人間でありながら「人でなし」といわれてしまった作中主体。「人でなし」と「人面鳥」の対比は、鳥と人との区別を曖昧にしていきます。その結果、人間を頂点とした人為的な〈生物ヒエラルキー〉は崩される。別言すれば、鳥と人とが等価になってしまうことで、鳥と人が〈入れ替え可能〉になってくる。そうであれば、鳥面人が「鳥でなし!」と告げられるケースも出てくるかもしれませんね。
押し花と一緒に眠る押し毛皮 同上
剥製があるのだから「押し毛皮」があっても不思議でありません。上掲句では、「押し花」と「押し毛皮」が並べられることにより毛皮と花のあいだにある上下差別が突きつけられ、ひいては、〈生物ヒエラルキー〉が問われてくる構造があるのではないでしょうか。先の「人面鳥」の句もこの「押し毛皮」の句も、一種の寓話として読むことができそうです。
階段に壁に厠に蚊の睡り 野口る理
「蚊ってさ ほとんどの時間休んでんだよ 壁や天井で」
笹野高史さんが出演しているKINCHOのCMを思い出しました。もうひとつ思い出したものがあります。それは、大正末期〜昭和初期に「新興川柳」を牽引した川上日車の「天井へ壁へ心へ鳴る一時」という句です。野口句は「AにBにCにDだ」、日車句は「AへBへCへ(Eする)Dだ」と似通った構文になります。ただし違いもあります。野口句では、A〜Dまですべて対象物として距離を置いているのにたいし、日車句では、自分の「心=C」をも経由してからDに収斂されていきます(もちろん野口句も「蚊の眠り」に意識を向けることでそれが自分の心に反ってくるのだ、という物言いもできますが、その議論は煩雑になるので無視します)。対象を対象のまま読者に手渡すか、対象をいったん作中主体が引き受けてから読者に手渡すか。ささいなことですが、それによって質感に微妙な違いが出てくるのが興味深いです。
天然の月代ですねと言うてくれる薄毛の軍師バーバー黒田 石原ユキオ
モノレール廃線したる悔しさに夜毎ふるえる高尾アパート
★★★★★ヘッドスパ最高でした。また来年きます。(おさかべ・年齢ひみつ♡)
アーモンドバターひと瓶費やして結い上げられた甘やかな髷
手柄山展望喫茶回転が速まりついに消えてしまった
“BARBER KURODA”から姫路ゆかりの黒田官兵衛を連想し、そこから高尾アパート、おさかべ姫、Mucheのアーモンドバター、手柄山と、姫路愛あふれる姫路づくしで構成されています。連作「アーモンドバター」は、まるで漫画のようなテイスト。軍師官兵衛が理髪師だったり、妖怪おさかべ姫がお客さんだったり、アーモンドバターで髷を結ったり、戦国時代と現代がシンクロしていたり。とても楽しく読みました。
歌壇には、わりと生真面目なひとが多いのか、切実な境涯とか実存を問うような連作がずらっと歌誌に収録されることも少なくありません。もちろん、重たい作品には重さゆえの良さがあります。でも、その合間に「アーモンドバター」のような連作が掲載されていたら、いい感じに抑揚がついて読みやすくなるのではないかしら。
良いことなのか悪いことなのか分からないけど、歌壇では、現実世界の論理を前提にした読み方がまだまだ主流である。でも、ここ十五年くらいだろうか、「この作品は現実の論理で読むべきか、漫画のように読むべきか」をごく自然にギアチェンジできる読み手が増えてきたと思います。今後はきっと、「アーモンドバター」のような甘さとコクと香ばしさを兼ね備えた、新傾向の短歌が増えてくる気がします。
(つづく)
Posted by wh at 0:03 0 comments
2015-12-20
【週俳10月・11月の俳句・川柳を読む】柳人・このわかめ的なるもの 飯島章友
【週俳10月・11月の俳句・川柳を読む】
柳人・このわかめ的なるもの
飯島章友
文芸評論家・劇作家・演出家の福田恆存は、自身のことを「カソリックの無免許運転」と言っていた。福田めかして言うならば、文芸としての川柳は〈五七五の無免許運転〉である。したがって柳人は〈五七五の無免許運転者〉と言える。ここでいう無免許とは、俳句でいう季語のような〈その文芸の表現を支えるツールがない〉ということだ。
まあ、それが川柳の魅力だと思うし、私自身も季語という制約がないので川柳を選んだくちだ。しかし、無免許のまま五七五を運転することに不安をおぼえないはずはない。もちろん、何年も無免許運転をつづけていれば、(このままずっといけるのではないか)という安心感が徐々に台頭してきて、いつしか不安はうすれていくことだろう。ところが、潜在意識に一時保管された不安は、とつぜん夢にあらわれて意識をさいなむことがあるのではないか。それは柳人もおなじだ。季語という免許がある俳句と向き合ったときなど、無意識の深淵から不安が顔をのぞかせる。不安なんてなーんもないよ、という言葉に騙されてはいけない。川柳で真面目に遊んでいる人ならば、誰でも一度は川柳の無免許性にほんろうされる。
さて今回の榊陽子の連作について私は、〈五七五の無免許運転〉にほんろうされる柳人の姿を「わかめ」に託し、戯画化したものと捉えてみた。軸の定まった地上の草木と違い、わかめは海のざわめきを柔らかく受けとめるように漂う。いろいろなキャラクターへ自由に変じ、なおかつ「なな子、社長ほか代用可」を演じられるのは、わかめくらいしかない。
泣いたってわかめわかめのショウタイム
なぜこの句の〈わかめ=柳人〉は泣いているのだろうか。思うにそれは、〈ショウ=川柳〉を演じるにあたって、〈わかめ=柳人〉が確固たる表現ツールをもっていないから不安なのだ。
「どこまでが俳句か、俳句の方で決めてくれ。それ以外は全部川柳でもらおう」というのは、川上三太郎という著名な柳人の言葉。定型以外これといった約束事がない川柳の自由さは、人びとを勧誘するときの売りにもなっている。しかし、表現にどん欲な柳人であればあるほど、自由というだだっ広い荒野で自分がどんな表現をしていけばいいのか不安が頭をもたげてくるものである。
また、ひとはよく自由について語る。そこでもひとびとはまちがっている。私たちが真に求めているものは自由ではない。私たちが欲するのは、事が起るべくして起っているということだ。そして、そのなかに登場して一定の役割をつとめ、なさねばならぬことをしているという実感だ。なにをしてもよく、なんでもできる状態など、私たちは欲してはいない。ある役を演じなければならず、その役を投げれば、他に支障が生じ、時間が停滞する――ほしいのは、そういう実感だ。(福田恆存『人間・この劇的なるもの』 新潮文庫)
俳句には〈季語の本意〉という言葉があると聞く。〈本意〉というくらいだから、いかに俳句で季語が要となっているかが想われる。俳人にとって季語とは、「ある役を演じなければならず、その役を投げれば、他に支障が生じ、時間が停滞する」というときの「役」に相当するのではないのかしら。俳句の門外漢である私からみても俳句の季語は、作品の成否にかかわる重要な役割を担っているように思われる。
いっぽう、川柳はどうだろうか。五七五の枠の中であれば「なにをしてもよく、なんでもできる」文芸だ。そのため、「なさねばならぬこと」を川柳が書き手に提供してくれることはない。言いかえれば、川柳で何を表現したいかは自分で見つけるしかないのだ。私自身、川柳を作句しはじめて二年間くらいは、川柳という自由な文芸を嬉々として楽しんでいた。ところが、創作的な自我が芽生えてきた三年目あたりから、〈自らに由〉って表現を確立しなければならない難しさを感じるようになったものだ。上掲句の〈わかめ=柳人〉も、〈ショウ=川柳〉における表現の確立がもてぬもどかしさで泣いているように思われる。
なんぴともわかめ涅槃を想像す
自分が〈ショウ=川柳〉で本当にやりたいことはなんなのだろうか。「テロテロするわかめ」「ふえるわかめ」「新宿のわかめ」といろいろなキャラクターを演じてはみたが、エステティックな手応えや実感はつかめぬまま、〈わかめ=柳人〉の苦悩はつづく。上掲句で「涅槃を想像」してしまうのには、そんな訳合がある。ただこの句では「なんぴともわかめ」といって、他者と自分の共通性を感じとっている。季語をもたない〈わかめ=柳人〉に苦悩があるように、季語をもった俳人にもそれに応じた苦悩があるはずなのである。
テンガロンハットも似合うわかめかな
どんなキャラクターにも自由に変じられる〈わかめ=柳人〉にとって、アメリカのカウボーイを演じることなどお手のものだろう。そればかりではない。時として俳句を演じてみせることだって可能だ。いわば「季語や切れ切れ字も似合うわかめかな」である。川柳でもふつうに季節の言葉や文の切れ目、そして切れ字とおなじ助詞は使われる。そのとき柳人は、一見して判別が不可能なくらい俳句とよく似た川柳をつくっている。つまり、俳句を演じることができるのだ。
なんとかして絶対的なものを見いだそうとすること、それが演戯なのだ。ちょうど画家が素描において、一本の正確な線を求めるために、何本も不正確な線を引かねばならぬように。(上掲書)
季語や切れ、切れ字も似合う川柳が川柳として正確なのか不正確なのか、私にはとうてい分からない。しかし、川柳としての手応えや実感を得るためには「何本も不正確な線を引」くことが必要になってくるだろう。そう考えたとき、カウボーイを演じることも俳句を演じることも、けっして無駄にはならないのである。
泣いたから訊けばわかめにゃ顔がない
冒頭の「泣いたってわかめわかめのショウタイム」と対になった句だろう。この連作は、冒頭で〈わかめ=柳人〉が泣く泣くショウに出演する姿を読者に示したあと、その〈わかめ=柳人〉の過去に遡り、さまざまなキャラクターを演じてきた軌跡を描出する。そして最後、上掲句でふたたび冒頭の場面に戻り、〈わかめ=柳人〉が泣いている理由は「顔がない」ためだと明らかにする。ここでいう「顔」とは、福田にしたがっていえば「ある役を演じなければならず、その役を投げれば、他に支障が生じ、時間が停滞する」実感のことである。
最後に、榊陽子本人の文章を引用してみたい。今回このような連作を創った意味がそこはかとなく分かる気がするからだ。
わたしは、さあ、作るぞ!とパソコンに向かって川柳に取りくみます。つまり作句前に〈言わんとすること〉がまず無きに等しく、それは作っている過程でうっすらと見えてくることもありますし、出来上がった瞬間見つかることもあります。かと思えば最終的に意味らしきものも見当たらないのに理由もなく、これでよし!と合点がいけば意味なんかくそくらえと思ったりもします。(平成27年10月発行「川柳木馬」第146号の「作家群像 榊陽子篇」より)
なお、私がこの文章で使用した〈わかめ=柳人〉という言葉は、〈榊陽子〉に代用可であることを付記しておこう。
後篇:
番外篇:正義は詩じゃないなら自らの悪を詠い造兵廠の株価鰻上り
Posted by wh at 0:05 0 comments
2015-03-15
【週俳・1月2月の俳句を読む】川柳はストリートファイトである 飯島章友
【週俳・1月2月の俳句を読む】
川柳はストリートファイトである
飯島章友
太箸に栗きんとんの甘さかな 小野あらた
読みおえて、一瞬(おや?)と思った。その(おや?)の由来を考えてみたところ、「太箸」ではさんでいるのが「栗きんとん」という物体ではなく、「甘さ」という感覚だからなのに気がついた。ふつう、箸ではさんだ時点では物体的な「栗きんとん」が意識される。ところが、上掲句では一足飛びして味覚が意識されているのだ。
まあ実際は、栗きんとんが甘いことは周知の事実だし、また、とろりとした餡の形状はすでに甘味を体現しているので、太箸にはさんだ時点で「甘さ」はじゅうぶん意識されるのではあるが、そういうことを抜きにしても、これは短詩型ならではの面白い措辞だなと思った。散文でこの妙味は出ない。外山滋比古著『省略の詩学』に、「ヨーロッパの詩はことば、思いを、つみかさねてつくる。建築的である。それにひきかえ俳句は、ことばも詩想も、できる限り削り落とす。彫刻的である」と書かれているのを思い出した。
鼬得て温もりゆけり鼬罠 花尻万博
「鼬得て温もりゆけり」という妖しい措辞に魅了された。鼬罠に意志が宿るかのような「鼬得て」、カメラをフィックスしたまま移ろいを静観する「温もりゆけり」。「ゆけり」という未来へつづく表現が情の侵入を防いでいる。かりに「温もりゐたり」としたばあい、表現に少しく情が入り込んで、やや通俗的になってしまったかも知れない。
「鼬得て温もりゆけり」と移ろいに軸をおいた措辞をとってきて、一旦〈切れ〉をおく。ホースの先をつまむと水が遠くへ飛ぶように、掲出句も〈切れ〉によってそれまでの移ろいに圧力がかけられ、そのうえで全体像の「鼬罠」が明示される。そのときの「鼬罠」はどうだ。人間の情など寄せ付けない圧倒的な存在感で立ち顕れてくる。
緑と白の境が葱のなきどころ なかはられいこ
川柳はストリートファイトである。ストリートファイトとは街で行われる素手の喧嘩だ。顔面にこつこつパンチを出しておき、相手のボディががら空きになったところへ強烈な一発を放つのは専門家のボクサー。対してストリートファイター(川柳人)は、自分のセンスだけを信じて思いもよらぬところからパンチを放ってくる。ボクサーは具体的技術をもつが、ストリートファイターにはない。それはちょうど「我が拳は我流、我流は無型、無型ゆえに誰にも読めぬ」と言った、『北斗の拳』に出てくる戦士〝雲のジュウザ〟みたいだ。
上掲句はストリートファイター的なセンスが光る一句。具体的な裏付けはなくともみごとに直感で葱の弱点を察知し、すかっとするほど強烈な一発を入れてみせた。
約束を匂いにすればヒヤシンス なかはられいこ
東直子の第一歌集『春原さんのリコーダー』の冒頭近くに、
ひやしんす条約交わししゃがむ野辺あかむらさきの空になるまで
という短歌がある。「ひやしんす条約」だけではそれが何なのかは分からないが、三句目「しゃがむ野辺」からの内容を見れば、その条約がどんなものだったかを想像できる構造になっている。東はストリートファイター的なセンスを短歌に持ちこんだ歌人だと勝手に考えているのだが(東直子ファンの方々に怒られそう……)、短歌形式によって必然的にボクサー的な裏付けが表れている。
だが、なかはらの句の「ヒヤシンス」には、その匂いのヒントとなる具体描写がない。短歌と違い下の句77がないのだから当然だ。裏付けのないままヒヤシンスが直接読み手に投げ出されている。その意味で上掲句もストリートファイター的だ。しかし、この句のばあいはストリートファイターなりの経験知がうかがえる。それは何かというとヒヤシンスの音の効果だ。たった五音の中に「ひ」「し」「す」と無声音が3つもある清らかで果敢ない音質、そして「今夜はとってもヒヤシンス」と言葉遊びなどでも使用される「ヒヤ」の涼感。そういうヒヤシンスの音的要素によって句中の「約束」は、あたかも、渡すことが出来ないままひんやりと、そしてひっそり抽斗に蔵われつづける古い恋文のような質感へと昇華された。
ボタンにしか見えないものを押している 兵頭全郎
今回はモノボケ、ホロホロとポロポロ、双子の子など、似たモノ同士の関係性から発想された句群と捉えてみたが、だからといってそれを共感性へと結実させる方向には構成されていない。これは兵頭のスタイルの特徴といえるのだが、傍から見るとたいへんストイックに思える。
いまの川柳界にはずいぶんと善い人たちが集まっている。清貧、忍耐、労り、家族愛といった要素を組み合せれば〝川柳さん〟という人格が出来上がりそうなくらいに。そんな善い人たちが川柳をつくればどうなるか。たとえばだが、「ボタンには見えぬボタンを押している」と書いて戦争の脅威をほのめかし、「むぅ、過去に学ばない政治家をうまく皮肉っておる」「然り然り」といった共感を得ようとするだろう。たしかにそれは戒めとして拳拳服膺すべきことではあるが。
ところが、兵頭の句のように最初から「ボタンにしか見えない」といわれたらどうだろう。ボタンに見えないモノを押す→実は爆弾のボタン、という固定的イメージがあるその分だけ、読み手は肩透かしを食う。「ボタンにしか見えない」という措辞に込められた裏の意味を探し出そうとしても、「ボタンにしか見えない」レベルを離れることはできない。何というかこれは、プロによる緻密な犯罪と思いきや10代の少年による素朴な犯罪でした、というケースに似ているかも知れない。そう上掲句は、「ボタンにしか見えない」などと純朴に、あるいは冷徹に、あるいは馬鹿真面目に言っている事態を楽しめればよいのである。それは、いわゆる〈膝ポン川柳〉の共感性とは別次元の楽しみ方だ。
水捌けのよいロゴマーク的月夜 兵頭全郎
ロゴマークに月といえば〈花王〉を思い出してしまうが、それはさておき、「ロゴマーク的月夜」とは冷静に考えると面白い。ロゴマークは社名や商品名などをデザイン化したもの。したがって、語順からいうと何かの名前を受ける形で使われることが多い。たとえば「花王のロゴマーク」「花王的ロゴマーク」という形であり、上掲句でいうなら「月夜的ロゴマーク」となるのが順当に思える。ところが、ここでは逆転している。そのため、じつは月夜の方がロゴマークであり、ロゴマークが月夜であるかのような倒錯性が生まれる。と同時に、ロゴマークと月夜の領域の水捌けがよくなった分、「水捌け」「ロゴマーク」「月夜」の各語がぜんぶ流れてゼロに帰する不思議な感覚がおとずれる。
え戦争俺のとなりで寝ているよ 赤野四羽
上掲句は電話を受けての台詞と捉えてみた。電話の相手は「戦争」の行方を探して、心当たりのある所に電話をかけまくっていたのだろう。緊急事態なのである。にもかかわらず、主人公は戦争に添い臥しながらあっけらかんと「え戦争」という。添い臥す相手とは、通常ならば子供、妻、恋人、愛人などが考えられるが、主人公と戦争との距離感・関係性がそのまま現代への批評につながっている。
野口あや子の第一歌集『くびすじの欠片』にこんな短歌がある。
戦争よやあねいやあね水槽に金魚の餌をこぼせば匂う
「やあねいやあね」という口調は、戦争を〈他人事〉と思いたい主人公のあり方が提示されており、それが三句目以降の具体描写によって示唆的に補強されている。いかにも芝居がかっている。だが、70年間戦争がなく、貧困とはいえ飢え死にすることもなく、あらゆる価値の相対化が促進され平均化されようとしている現在、主人公を道化にすることでしか自らの立ち位置を、ひいては社会一般の状況を逆照射する方法はないのかも知れない。
第405号
■小野あらた 喰積 10句 ≫読む
第406号
■花尻万博 南紀 17句 ≫読む
第409号
■なかはられいこ テーマなんてない 10句 ≫読む
■兵頭全郎 ロゴマーク 10句 ≫読む
■赤野四羽 螺子と少年 10句 ≫読む
Posted by wh at 0:04 0 comments
2014-08-24
週刊俳句・柳俳合同誌上句会 2014年8月
週刊俳句・柳俳合同誌上句会 2014年8月
10名様参加。5句選(特選1句・並選4句)。≫投句一覧
参加者
〔柳人〕
飯島章友
きゅういち
清水かおり
なかはられいこ
八上桐子
〔俳人〕
相子智恵
笠井亞子
谷口慎也
鴇田智哉
中村安伸
【砂】
このへんがたぶん砂場の性感帯 飯島章友
○谷口慎也
○きゅういち
○笠井亞子
○清水かおり
■砂場のとらえどころのない重要なポイント、を言って妙味。(清水かおり)
■砂は変幻自在にして官能的。砂場にそれを発見した作者の嬉しそうな顔がまず浮かんだ。「このへんがたぶん」という間の持たせ方も狡猾。(笠井亞子)
■「砂場の性感帯」を見つけた時点で完成をみたであろう句、「このへんがたぶん」に冗長さとものたりないものを感じたのだが、かえって言い過ぎぬ姿勢が句を立たせたか。(きゅういち)
■手のひらに触れるくすぐったい砂の感触が〈性感帯〉という言葉を導き出した。〈たぶん〉にはその言葉に対する作者の含羞を見てもよいが、この措辞によって一句は、程良い調和を伴った愛らしいものとなっている。(谷口慎也)
ちょっとした砂丘になって待っている なかはられいこ
◎谷口慎也
◎鴇田智哉
○中村安伸
○相子智恵
■待っている間に、自分が砂の溜りになってゆき、小さな砂丘になったということだろう。そのとらえ方が面白い。
演劇か何かの開演を待っているのかとも思ったが、そうではないだろう。〈ちょっとした〉という軽い言葉遣いからは、人を待っている感じがするからだ。〈ちょっとした〉という言葉に、親しみのある相手に対する軽い「抗議」の感じがあるのである。漫画における、「いらだち・怒り」の表現として、額に十字路マーク(?)が出るというのがあるが、主人公は額にあんなマークをつけたまま、にっこりと相手を迎えたのではないか。(鴇田智哉)
■〈ちょっとした砂丘〉の言い回しが軽妙かつ洒脱。同時に〈砂丘〉が「待つこと」にまつわる期待や不安感のようなものまでも表出している。多くを語らず多くを感じさせる理想的な一句である。(谷口慎也)
■なんだか暑そうな場所で、相手にずいぶんと待たされているのかもしれません。
待つうちに、相手に対する心が乾いていく。「ちょっとした砂丘」が絶妙な距離感のように思いました。(相子智恵)
■砂丘という隠喩で心中の渇きを示すのは、やや常套的といえなくもないが「ちょっとした」のキュートさに惹かれた。(中村安伸)
■約束の一分前もしくは一分後くらいかしら。(飯島章友)
■ちょっとした(小)砂丘(大)でも砂丘は足を踏み入れると・・私達は作品の中で何かになることが多いが砂丘になるのは新鮮な感覚。(清水かおり)
顎を手に乗せる身内の砂が降る きゅういち
○鴇田智哉
○中村安伸
○飯島章友
■身内は「からだの内部」や「からだじゅう」の意と、「家族」「親族」の意があります。しかし、無理がないのは前者の「からだの内部」の意味だと思われ、そうだとすれば「顎に手を乗せ」て苦慮することが「砂が降る」を導き出す措辞になっているのではないでしょうか。(飯島章友)
■何気ない動作と心象を重ねた。「落ちる」や「こぼれる」でなく「降る」を選んだのは、物思いの継続することを示すのだろう。(中村安伸)
■〈身内〉は〝からだの中〟という意味でとった。自分の〈顎〉だろう。つまり頬杖のような状態だ。しばしの放心。全身がシルエットになったかのような感覚に近いのだが、そのシルエットが石の塊のように静止したものでなく、降る砂であるところが面白い。均質でありながら動いている。(鴇田智哉)
■頬杖のことを「顎を手にのせる」と言っているのか、もっと想像力を働かせると、身内の誰かの葬送の一場面までも浮かんでくる(清水かおり)
砂こぼす月に目じりのようなもの 谷口慎也
○なかはられいこ
○八上桐子
○相子智恵
■三日月でしょうか。砂は月が流した涙のようで、幻想的な句だと思いました。(相子智恵)
■古くから「月の顔」と言われてきたように、月は顔だ。けれど、その目鼻は定かではなく、見るものが描き入れる。目じりさえあやふやなままに、確かにこぼれ落ちる砂。しずかな息づかいの迫る月から、目が離せなくなってしまった。(八上桐子)
■本来は「砂こぼす」で切れていると読むべきなんでしょうか。私は「砂こぼす月 に」とつなげて読みました。黄砂とか飛んでる真昼の白っぽい月か らま るで涙 のようにこぼれる砂。月に目じりをみつけたところが好きです。(なかはられいこ)
砂のなかのきみは砂鉄やぼくは砂金 中村安伸
砂めくれあがり揚羽の浮びたる 鴇田智哉
○谷口慎也○笠井亞子
■実景ともとれるムリのないシュールさがある。砂の劇場を見ているようだ。(鳥取砂丘を背景に作品を撮り続けた写真家のことを思う)「浮びたる」が揚羽の登場を格調高くしていて印象的。(笠井亞子)
■砂場でも海辺でもかまわないが、〈揚羽〉はまるで潜水艦のように浮上してくる。普段の何でもない生活の中でこういう「突然」にはよく出くわすものだ。しかしそれらがこの句のような言葉で表出されるとき、一句は虚実皮膜の不可思議さを醸し出す。(谷口慎也)
■砂→揚羽という発想は好きです。(飯島章友)
■時空を越えて現れた揚羽はその頃のせつない想いを留めている。砂はめくりあがるものなのかと妙に納得を誘う作品。(清水かおり)
上空の砂なら多民族でした 清水かおり
○飯島章友
■上空の砂「なら」多民族と言うんですから、一民族の地に住む人間が上空に舞ってきた砂を仰ぎ見て、多民族共生社会に思いを馳せた句かも知れません。しかし、たとえば中国大陸内陸部で発生する黄砂は他民族に健康被害を引き起こす困った物質ですし、また社会的なことを言えば、移民との軋轢の問題は多くの国が抱えています。上掲句からは多民族性が内包する憧憬と辛さとを感じます。(飯島章友)
■面白い句だと思ったが、しばらくすると「上空の砂=多民族」の意味的な構図が目立ってきて、一句はそこから動かない。この簡潔な断定を惜しいと思ったので、敢えて抽出してみた。(谷口慎也)
朝のシーツにランゲルハンス島の砂 八上桐子
◎清水かおり
◎笠井亞子
◎中村安伸
◎飯島章友
○きゅういち
○なかはられいこ
■朝のシーツとランゲルハンス島は現実物、そこに砂が合わされると幻想と現実のあわいが出現する。思わず手をぎゅっと握ってしまう。村上春樹の小説世界にごく自然に繋がっている作品。(清水かおり)■夢の中で訪れたビーチの砂が寝床に残されているという幻視と、その砂浜が「ランゲルハンス島」のものだったという言葉の遊戯。
臓器に「島」と名づけた語の喚起力によって、二重の跳躍が可能となった。(中村安伸)
■「砂」という言葉をつなげただけで「ランゲルハンス島」の意味が全く変わってしまう詩的面白さ。また、膵臓は実際に胆砂ができてしまうこともあるそうで、リアリティーをも感じます。(飯島章友)
■ランゲルハンス島というと複雑なイメージになりがちな所、「砂」という限定のお陰で、なんだかポップかつシュールな一句となった(ランゲルハンス島というのが実在の島で、ヴァカンスに出かけていたかのような)。
季語は無いけれど夏の朝の感じが横溢。バックには『マルタ島の砂』が流れている…。(笠井亞子)
■村上春樹と安西水丸の「ランゲルハンス島の午後」というエッセイ集を思い出し ました。夢のなかの出来事が、砂によって実体化されたようにみえ ておもしろ いと思いました。でもよく考えたら、マズイいんじゃないでしょうか、そこの砂 は。病院で検査してもらうことをお勧めします。(なかはられいこ)
■掲出句は特選にも押せるのではないかと感じ入ったが、「ランゲルハンス島」は膵島との意、意味を調べた小生に非があるのだが、急激に句の神秘性が薄らいでしまった。(きゅういち)
熱帯魚吐きたる砂や砂に落つ 相子智恵
○笠井亞子
■魚の口から吐かれた砂が水槽の底へ落ちていく、それだけのこと。
そのスローモーションじみた景はしかし「夏の時間」をひどく意識させる。(笠井亞子)
蒟蒻は砂の模様ぞ南風吹く 笠井亞子
○鴇田智哉
■まず、蒟蒻のあの色合いを〈砂の模様〉と言ったことで、一瞬、乾いた状況が浮かんでしまう。これは、食べ物である蒟蒻の印象としてはマイナスだ。食べ物としての蒟蒻の命は水分だと思うが、その逆のイメージだからである。〈砂の模様〉は、はっきり言って、おいしそうではない。だが、〈南風吹く〉と景色を広げたことで、その〈南風〉が雨雲をはらんだ湿気のあるものであるような気がしてくる。〈蒟蒻〉という奇妙なもの。そのありようを、どんよりとした質感でとらえているところが面白い。農産物である蒟蒻の、素朴な質感があると思う。(鴇田智哉)
【本】
エロ本をしぼればにおう鎮守様 きゅういち
○なかはられいこ
■「エロ本」と「鎮守様」の取り合わせが新鮮でした。性的なものと祭祀って無理 なくつながるようにも思えます。「エロ本」という俗っぽい言葉も 「しぼれ ば におう」という中七(しかもひらがな表記)でによって、柔らかくて水っぽくて 生々しくも神聖なものに変体してて、そこもおもしろかったです。(なかはられいこ)
■鎮守様の御座す神社、昔の村落共同体であればあんな事やこんな事の場になっていたかも知れません。(飯島章友)
永き日のひとつでありぬ古本屋 谷口慎也
○相子智恵
■春の日永。日差しのやわらかい景色の中に、古本屋ものどかに佇んでいる。古本屋というのがいいなあと。(相子智恵)
■良質な邦画のような句。(飯島章友)
逝く夏の線一本の星座かな 相子智恵
■流れ星・・だろうか。「逝く」の措辞がさびしい。(清水かおり)
転写本だからワサビも添えておく 飯島章友
○清水かおり
■転写本に何かを加味すると転写本といえなくなるかもしれないが、あえてワサビを効かす発想の面白さ。転写作業に辛みや風味を効かせたいと思う主体の情熱がいい。
「だから」と気の抜き方が絶妙。(清水かおり)
豆本をつまむ守宮をつまむように 笠井亞子
○鴇田智哉
○中村安伸
■守宮を対比させたことにより、豆本のもつ奇妙さ、ものめずらしさ、デリケートさがクローズアップされ、腑に落ちた。(中村安伸)
■動詞にはいろいろニュアンスがあって、「つかむ」というとかっこいいけれど、「つまむ」というとちょっとオドケた感じがする。「ひょいとつまむ」の「ひょいと」みたいなニュアンスが、「つまむ」自体に備わっているのだ。で、この句は、その〈つまむ〉の感覚がよく出ていると思う。
ところで、(俳人の性として申し訳ないが、)〈守宮〉が比喩として使われているため、厳密にいうと無季の句となっている。〈豆本〉と〈守宮〉を入れ替えて有季の句としても、内容けっこう面白い。でも、原句も面白い。
結局、〝〈守宮〉を持ったときに〈豆本〉を思い出す感覚〟と、〝〈豆本〉を持ったときに〈守宮〉を思い出す感覚〟のどちらが面白いか、ということが問題である。面白さでいえば、どちらも同じぐらい。でも、二者のどちらであるかによって、作者のキャラクターは結構違う。
この作者は、〝〈豆本〉を持ったときに〈守宮〉を思い出す感覚〟の方の人なのだ。仮に無季であろうが、作者がそうなのだから、こちらでよい。(鴇田智哉)
■守宮をつまんだことはないが、「つまむ」で豆本と守宮を同列した作者のユーモアを感じる。(清水かおり)
本よりも眩しく蟻の地がひらく 鴇田智哉
○清水かおり
■蟻地獄は時にパラダイスかもしれないと思う。「眩しい」に人間深層心理が言いつくされている。(清水かおり)
■本の活字と蟻との類比か。寺山修司を想いました。(飯島章友)
本降りになって桃缶買いに行く 清水かおり
◎相子智恵
○谷口慎也
○八上桐子
■「本降り」と「桃缶」の偶然の組み合わせが好きでした。
桃缶、よほど食べたかったのですね。缶の中の、シロップでずぶぬれの桃缶の桃と、本降りの中の自分がシンクロします。
雨は決して冷たくなく、シロップのようにまとわりつくようです。(相子智恵)
■「そんなヤツおらんやろ」と、まずは突っ込んだ。ところが、いる気がしてくる。にしても、桃缶。どうしても食べたくなるか?重いし。が、そんな日が来そうな気がしてくる。いえ、来て欲しい気すらしてくる。なつかしい衝動が、呼び覚まされたのだ。そんな日はあったのだ。(八上桐子)
■〈本降りになって出て行く雨宿り〉という古川柳がある。これは他者に対する揶揄。だが〈桃缶〉となれば話は別。一方で、三鬼の〈中年や遠くみのれる夜の桃〉があり、併せ読めば、それが「缶詰」であるというところに一種の滑稽とそれに伴う哀感さえ覚えるのだが、やや読み過ぎか?(谷口慎也)
■たとえば刺身を食べようとしたとき醤油がないことに気づいたら、これは即刻買いに出掛けざるをえません。でも「桃缶」という嗜好品は醤油ほどの必要性を感じない。要するに、私的な拘りで思い迷っている内にとうとう「本降り」になってしまったという顛末。パイン缶や蜜柑缶に比べ、桃缶には蠱惑的な何かがありそうです。(飯島章友)
本体を待っている間のくすりゆび なかはられいこ
○きゅういち
○中村安伸
■朦朧とした書き方なのでさまざまな解釈が可能だが、本体に先んじて届けられた付属品をくすりゆびでもて遊んでいるのだと読んだ。
待つ心情が指に投影されてエロティックな風情もある。くすりゆびも本体というよりは付属品に近いものだろう。(中村安伸)
■どこかに漂うエロス、おそらく「くすりゆび」の持つ一般的なイメージによるものではないかと感じるが・・・一部分が全体を待つという大きな世界観が凝縮されている。(きゅういち)
■この「くすりゆび」が仮に左手薬指なら愛の証である指輪を待っている状況かも知れませんが、そのばあい「本体」という言葉はどうもしっくり来ない。「本体を待っている」という措辞からは、まるで義肢としての薬指が本体を待っている雰囲気があります。(飯島章友)
■これはもう小川洋子の「くすりゆびの標本」以外のシーンは浮かばない (清水かおり)
葉桜の独逸の本屋めく晩夏 八上桐子
冷房やひねもす本を抜きつ挿しつ 中村安伸
【音楽関連】
アサガオノカスカナカオススガシカオ 八上桐子
◎なかはられいこ
○きゅういち
○笠井亞子
■一瞬でがっちり掴まってしまいました。この句に裾を掴まれてしばらく身動きで きませんでした。ふつうに漢字とひらがなで書かれた句と比べて、 すべてカタ カナで書かれものは、目から脳に至る時間にどれほどの差が生じるのでしょう。 最初、カスカスとか、カオナシとか、スカスカとか読み 間違えながら「かすか なカオス」にたどり着いたときには、作者に嫉妬すら感じました。一句まるごと カタカナというのも新鮮ではありますが、た だそれだけではない、そのうえ間 違ってもキワモノなんぞとは言えない、詩的完成度の高い一句だと思います。(なかはられいこ)
■カタカナ表記、音韻の繰り返し等句自体に音楽が流れるようで遊び心満載、作句自体を楽しむような句姿に思わず「まいった」とつぶやいてしまうが「カオス」がいかにもの感。(きゅういち)
■イミよりまず読みをうながすカタカナの力を十全に生かした句。17文字が、数えてみれば「アオカサシスナシ」の8文字で構成されている。
朝顔にある微かな混沌も、その(カスカスとした)リズムに乗ると、からっとしていて楽しげに見える。元々カタカナ表記である名前の力も大きい。(笠井亞子)
■カの力技! (清水かおり)
アリランを乙女と乙女口移し 清水かおり
◎八上桐子
■ぷるんとふくらんだくちびるが、くちびるを真似て歌うアリラン。ゆっくり吐き出される一音、一音が、甘く切なく溶け合ってゆく。「口移し」は性的イメージにも働くが、官能を超越した“気”の交感を感じさせる。一句に凝縮された、プラトニックなエロティシズムに陶然となった。(八上桐子)
■「アリラン」「乙女」「口移し」という言葉の美的関係性と、a音・o音・u音の韻がよい。(飯島章友)
ドラムロール西瓜落下の映像に 中村安伸
○なかはられいこ
○相子智恵
■変な映像にドラムロールが付いて、なんだかおかしくて、もの悲しい。どんな番組か気になります。(相子智恵)
■結果が惨事となることがわかっていながら、期待してしまうのが人間の哀しいサ ガですね。とか、西瓜だから気軽に言えるわけですが、地に激突し て、ぐ ちゃっ てなった赤から、いやでも想像できてしまうものがあって。ひとの意識 下にある残酷な部分を引きずりだすような、ちょっと怖い句な気がします。(なかはられいこ)
■ドリフのごとし。(飯島章友)
■永遠に続きそうなドラムロールは時間の流れを遮断するような感覚がある。西瓜の落下でもドラマティックな人生の一ページに為り得る。(清水かおり)
はんざきの歌声ありて水の音 笠井亞子
○八上桐子
○飯島章友
■「歌声」という言葉が「はんざき」と「水」を仲介し融合させる働きをしていると思います。歌は通常、楽しいから歌うものだと思いますが、はんざきが歌っている川はさぞかし澄んでいるのでしょう。(飯島章友)
■「はんざきの歌声」に意表を突かれるが、そこはまだ半信半疑。下5の「水の音」でせせらぎに変換され、一気にリアリティーを帯びる。せせらぎは歌いつづけ、透明な歌声が私を通過してゆく。はんざきに歌を授けた、作者の詩心に感謝したい。(八上桐子)
竿竹にCD盤と風鈴と 相子智恵
○鴇田智哉
■CDがぶら下がっている光景は、見覚えのある風景として定着しているだろう。あれは何を除けているんだったか、鳥? 猫? それはそうと、〈風鈴〉もぶら下がっているんだが、別に風流でも何でもないし、〈竿竹〉も竹じゃないし、きわめて味気ない風景が、「音楽」という題に対してちょっと面白かった。(鴇田智哉)
■「CD盤」がテクストにおけるちょっとしたクビレになっていますね。(飯島章友)
縦笛のかつてキリンであった跡 飯島章友
○谷口慎也
○きゅういち
■「縦笛」と「キリン」の共通項を読者へ無意識にイメージさせる仕掛け、一句の中に輪廻に通じる時間軸をも織り込みふわっとした読後感をいただいた。(きゅういち)
■〈跡〉にやや難点。それでは一句が閉じてしまうという思い。だが、〈縦笛〉が〈キリンであった〉とはよもや誰も思いつくまい。その直観・直覚に賛同。(谷口慎也)
■縦笛のあのボコボコとしたシルエットはキリンだったのかと納得する。(清水かおり)
上向きにすいつちょの声反りあがる 鴇田智哉
大蓮のまわり音楽止みにけり 谷口慎也
◎きゅういち
■流れていたであろう「音楽」が「大蓮」の回りのみから消える。大きな時間軸を感じさせ、なにも語らずその空間の持つ質感を端的に言い表している。(きゅういち)
帝国の鋪道の音の無いダンス きゅういち
○飯島章友
■帝国と言っても伝統や慣習を大切にし、民の生活の自由を守って国を治める帝もいますが、上掲句の帝国はそうでない雰囲気を感じます。「音の無いダンス」という具体でこの帝国の様子を想像させる手柄。(飯島章友)
■音のないダンスが国家の持つ危うさをうまく表現している。(清水かおり)
立秋の金銀パールプレゼント なかはられいこ
○八上桐子
○清水かおり
■思わず口ずさむ。洗剤のCMソングでこの半世紀中一番の印象深さだったフレーズからは、まず「主婦」を連想させる。残暑厳しい「立秋」に何がしかを思いめぐらす姿を詠んでいる。
庶民の小さな幸せと憂鬱が簡潔に同居する作品。(清水かおり)
■「立秋の金銀パ」まで読んだところで、あのメロディになった。立秋と読むだけで空気の澄むような、気温が2度ほど下がるようなイメージに、ソプラノの軽やかな響きがピタッと重なる。金、銀、パールのそれぞれの光も、秋を感じさせる。それにしても、金銀パールがよく出てきたと思う。(八上桐子)
以上・全30 句
2014-05-04
10句作品テキスト 暗転 飯島章友
暗 転 飯島章友
はじまりは回転寿司の思想戦
本日はお日柄もよく長い顔
雨雲が走るぬらりひょんが走る
義賊からとんからりんと予告状
気がつくと海豚一座の星である
暗転やしばし人形のみ光源
剥製の一羽くらいはクローン性
幻灯機倶楽部で兄をみうしなう
天帝の手紙静かなホバリング
夕映えの渚を駆けてゆく駝鳥
Posted by wh at 0:07 0 comments